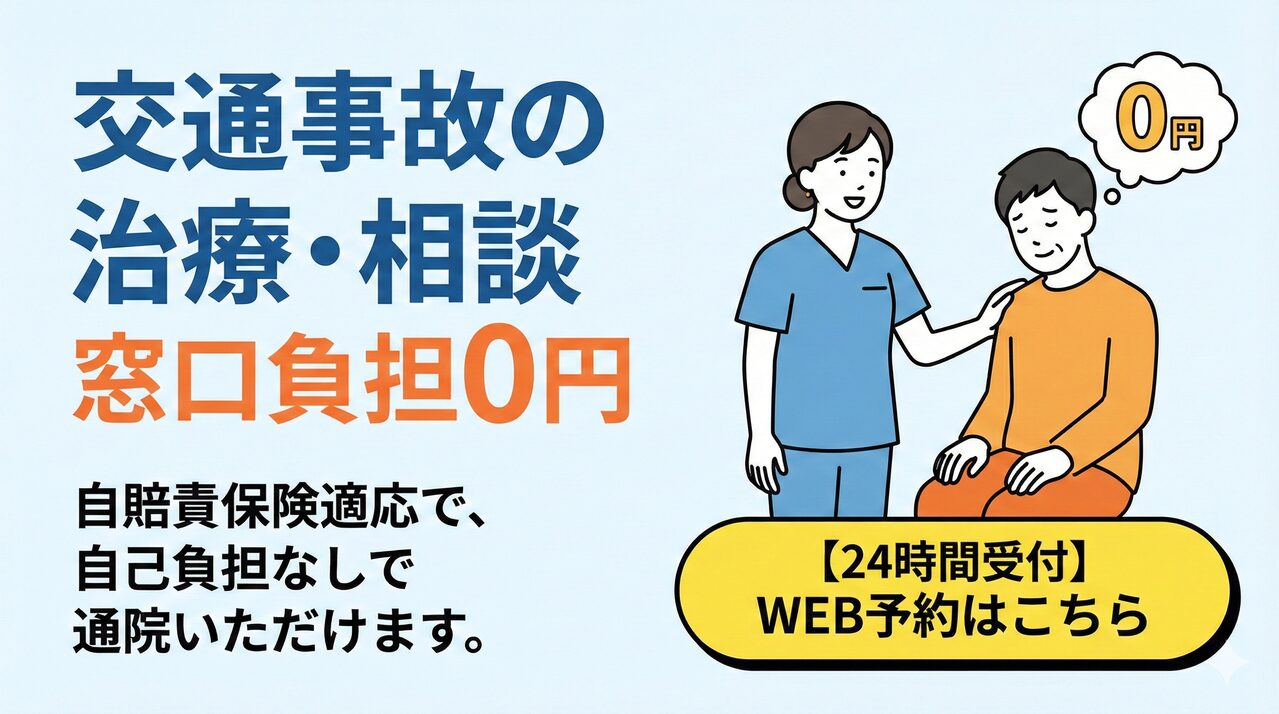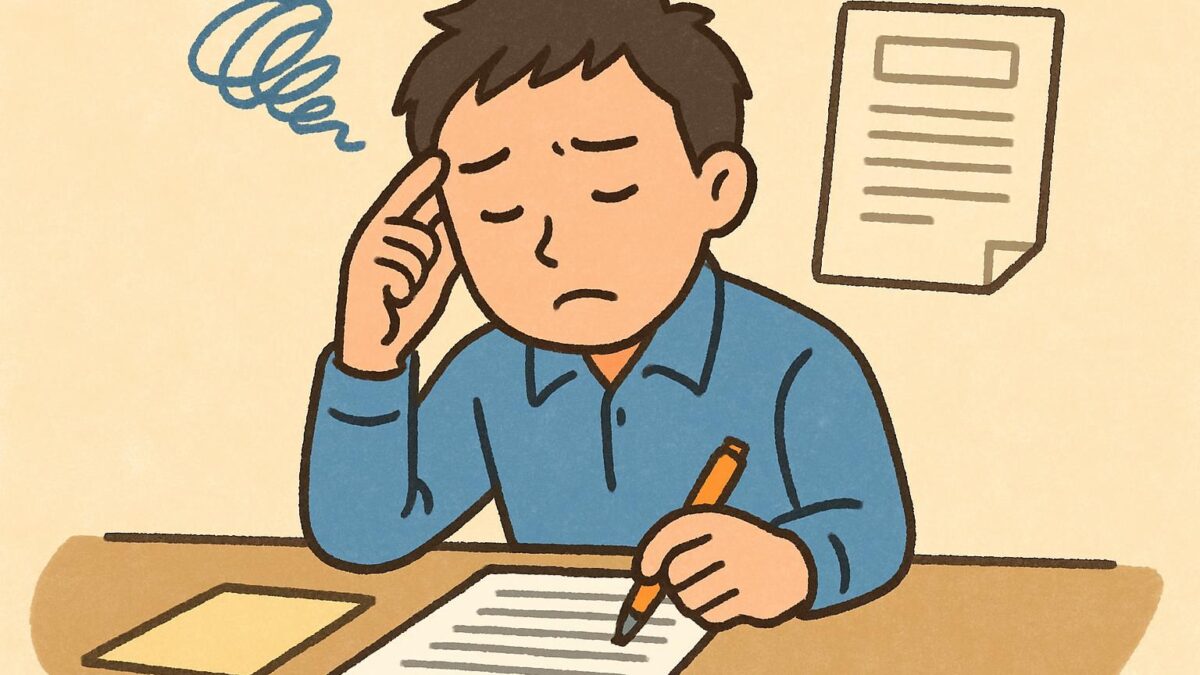交通事故の加害者となり、被害者へ支払った賠償金を後から自賠責保険に請求する方法が「加害者請求」です。この手続きが複雑そうで不安に思っていませんか?
加害者請求の具体的な流れから必要書類、注意点まで全てわかります。
正しい手順とポイントを理解すれば、支払った賠償金を取り戻す手続きをご自身でスムーズに進めることも可能です。加害者請求でお困りなら最後までお読み下さい。
自賠責保険の加害者請求とは? 被害者請求との違い
交通事故を起こしてしまった場合、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負います。その際に利用できるのが、すべての自動車に加入が義務付けられている「自賠責保険」です。
自賠責保険への保険金請求には、主に「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。ここでは、加害者請求の基本的な仕組みと、被害者請求との違いについて分かりやすく解説します。
加害者請求の基本的な仕組み
加害者請求とは、交通事故の加害者が、被害者に支払った損害賠償金を、自身の加入する自賠責保険会社に後から請求する手続きのことです。
つまり、加害者が一旦自己資金で賠償金を立て替え払いし、その立て替えた分を後から自賠責保険に補填してもらう、という流れになります。この請求は、加害者と被害者の間で示談が成立し、加害者が被害者へ賠償金の支払いを終えた後に行うのが一般的です。
被害者請求との主な違い
加害者請求と被害者請求は、誰が、どのタイミングで請求するのかという点で大きな違いがあります。どちらの方法を選ぶかによって手続きの流れや準備するものが変わるため、その違いを正確に理解しておくことが重要です。主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 加害者請求 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 請求する人 | 加害者 | 被害者 |
| 請求のタイミング | 加害者が被害者へ賠償金を支払った後 | 示談成立前でも請求可能 |
| 請求先 | 加害者が加入する自賠責保険会社 | 加害者が加入する自賠責保険会社 |
| 主なメリット | 加害者が主体となって手続きを進められる | 加害者との示談を待たずに賠償金の一部を受け取れる |
| 主なデメリット | 賠償金を一時的に立て替える必要がある | 損害額の立証などを被害者自身で行う必要がある |
このように、加害者請求は加害者が賠償金を支払った後に行うのに対し、被害者請求は被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に請求する方法です。
被害者は、加害者との示談交渉が長引いている場合でも、治療費などの当座の費用を確保するために被害者請求を利用することがあります。より詳しい情報については、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトも参考にしてください。
自賠責保険で加害者請求ができる具体的なケース
交通事故の加害者になってしまった場合でも、自賠責保険を使ってご自身が支払った賠償金の一部を取り戻せる可能性があり、これを「加害者請求」と呼びます。
では、具体的にどのような状況で加害者請求ができるのでしょうか。ここでは、加害者請求が可能な代表的なケースと、逆に請求できないケースについて分かりやすく解説します。
加害者が被害者に賠償金を支払った場合
加害者請求を行うための最も基本的な前提条件は、加害者がすでに被害者に対して賠償金を支払っていることです。例えば、加害者がご自身の貯金などから、被害者の治療費や休業損害、慰謝料などを支払い、その後に示談が成立した場合がこれにあたります。
加害者請求は、あくまで加害者が立て替えた賠償金を、自賠責保険の補償範囲内で回収するための手続きです。そのため、被害者への支払いが完了し、その金額を証明する領収書や示談書があることが絶対条件となります。
任意保険が使えないまたは未加入の場合
多くの場合、交通事故の対応は加害者が加入している任意保険会社が行います。しかし、以下のような理由で任意保険が利用できない、または利用しない場合に加害者請求が選択されることがあります。
- 任意保険に加入していない(未加入)
自賠責保険しか頼れる保険がないため、加害者自身で被害者と示談交渉を行い、支払った賠償金を自賠責保険に請求するケースです。 - 任意保険の補償対象外(免責)
飲酒運転や無免許運転といった重大な過失(法令違反)があった場合、任意保険では保険金が支払われない「免責事由」に該当することがあります。このようなケースでも、被害者救済を目的とする自賠責保険では、加害者が支払った賠償金に対して保険金が支払われる可能性があります。 - 任意保険を使いたくない
交通事故で任意保険を使うと、翌年度以降の保険料が上がる「等級ダウン」が起こります。そのため、損害額が比較的小さい事故の場合、保険料の値上がりを避けるために、あえて任意保険を使わず自費で賠償し、後から自賠責保険に加害者請求を行うという選択肢もあります。
自賠責保険で加害者請求ができない具体的なケース
一方で、加害者請求が認められないケースも存在します。勘違いしやすいポイントを以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
| 請求できない主なケース | 理由 |
|---|---|
| 被害者に賠償金を支払っていない | 加害者請求は、加害者が支払った賠償金を回収する制度のため、支払いの事実がなければ請求できません。 |
| 物損事故(物の損害)のみの場合 | 自賠責保険は、交通事故による人のケガや死亡といった「人身損害」のみを補償する保険です。車の修理代などは対象外です。 |
| 加害者自身のケガの治療費 | 自賠責保険は、他人を死傷させた場合の損害を補償する制度です。加害者自身の損害は補償の対象となりません。 |
| 請求権の時効が成立している | 加害者請求の権利は、加害者が被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年で時効となり、請求できなくなります。(※2010年4月1日以降に発生した事故の場合) 詳しくは国土交通省のウェブサイトもご確認ください。 |
【完全ガイド】自賠責保険の加害者請求の具体的な流れ
自賠責保険の加害者請求は、正しい手順を踏むことでスムーズに進めることができます。ここでは、交通事故の発生から保険金が支払われるまでの具体的な流れを6つのステップに分けて、誰にでも分かりやすく解説します。
ステップ1 交通事故の発生と警察への届出
すべての手続きは、交通事故の発生から始まります。事故が起きたら、まずは落ち着いて負傷者の救護と安全の確保を行ってください。その後、必ず警察(110番)に連絡しましょう。
警察へ届け出ることは、道路交通法上の義務であると同時に、自賠責保険の請求に不可欠な「交通事故証明書」を発行してもらうための必須条件です。この証明書がなければ、保険金の請求手続きを進めることができません。物損事故だと思っても、後から相手がケガを主張するケースもあるため、人身事故として届け出ておくことが重要です。
ステップ2 被害者への賠償金の支払いと示談の成立
加害者請求の大きな特徴は、加害者が先に被害者へ賠償金を支払う点にあります。被害者の治療が完了し、損害額が確定したら、被害者との間で賠償額について話し合い(示談交渉)を行います。
双方が合意に至ったら、その内容をまとめた「示談書」を作成します。示談書には、賠償金の総額や内訳、支払日などを明記し、双方が署名・捺印します。示談が成立したら、取り決めた内容に従って被害者に賠償金を支払います。このとき、支払ったことを証明する「領収書」や「振込明細書」を必ず受け取り、大切に保管してください。これらは後の請求で必要になる重要な証拠となります。
ステップ3 加害者請求に必要な書類の準備
被害者への支払いが完了したら、次はいよいよ自賠責保険会社へ提出する書類の準備に取り掛かります。加害者請求には、さまざまな書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
- 保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 示談書
- 賠償金の支払いを証明する書類(領収書など)
- 被害者の診断書や診療報酬明細書
この他にも、損害の内容に応じて休業損害証明書や後遺障害診断書など、追加の書類が必要になる場合があります。交通事故証明書は、地域の自動車安全運転センターで発行を申請できます。書類に不備があると手続きが遅れる原因になるため、漏れなく準備しましょう。
ステップ4 自賠責保険会社へ請求書類の提出
必要な書類がすべて揃ったら、加害者が加入している自賠責保険会社に提出します。どの保険会社に加入しているかは、自動車やバイクに備え付けてある「自賠責保険証明書」で確認できます。もし証明書を紛失してしまった場合は、契約した代理店や車を購入した販売店などに問い合わせてみましょう。
書類の提出方法は、保険会社の窓口へ持参するか、郵送するのが一般的です。提出先や方法については、事前に保険会社のウェブサイトや電話で確認しておくと安心です。
ステップ5 保険会社による損害調査の実施
請求書類が保険会社に受理されると、専門の調査機関である「損害保険料率算出機構」にて、損害内容の調査が行われます。この調査では、提出された書類をもとに、事故の状況や損害額、治療内容などが適正であるかが客観的に判断されます。
調査の過程で、書類の内容に不明な点があったり、追加の情報が必要になったりした場合は、保険会社から問い合わせや追加の資料提出を求められることがあります。調査が円滑に進むよう、誠実に対応しましょう。
ステップ6 保険金の支払い決定と入金
損害調査が完了すると、保険会社は調査結果に基づいて支払う保険金の額を決定します。決定した金額は「支払額決定通知書」などの書面で請求者(加害者)に通知されます。
通知された内容に問題がなければ、後日、請求時に指定した銀行口座へ保険金が振り込まれます。この入金をもって、自賠責保険の加害者請求に関する一連の手続きは完了となります。
自賠責保険の加害者請求に必要な書類一覧と入手方法
自賠責保険の加害者請求手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を漏れなく準備することが重要です。ここでは、すべての請求で共通して必要な書類と、被害の状況に応じて追加で必要となる書類を分けて、それぞれの内容と入手方法を分かりやすく解説します。
すべての請求で共通して必要になる書類
これからご紹介する4つの書類は、損害の種類(傷害・後遺障害・死亡)にかかわらず、加害者請求を行う際に必ず必要となる基本的な書類です。
保険金支払請求書
保険会社に対して保険金の支払いを正式に依頼するための書類です。加害者が加入している自賠責保険会社の窓口に連絡するか、公式ウェブサイトからダウンロードして入手します。請求者(加害者)自身が事故の状況や請求内容を記入し、実印を押印の上、印鑑証明書を添えて提出するのが一般的です。書類の名称は保険会社によって「保険金(共済金)支払請求書」など多少異なる場合があります。
交通事故証明書
交通事故があった事実を公的に証明するための書類です。警察に届け出た事故であれば、自動車安全運転センターで発行を申請できます。警察署や交番で受け取る「交通事故証明書申込用紙」を利用するか、自動車安全運転センターのウェブサイトからオンラインでの申請も可能です。通常、申請から発行まで10日ほどかかります。
示談書
加害者と被害者の間で、賠償金額や支払い条件について合意(示談)が成立したことを証明する書類です。決まった書式はありませんが、「いつ、どこで、誰が起こした事故か」「示談金額」「支払い方法」「今後お互いに金銭的な請求をしないこと(清算条項)」などが明記されている必要があります。示談が成立した日付と、当事者双方の署名・捺印が必須です。
賠償金の支払いを証明する書類(領収書など)
示談に基づき、加害者が被害者へ賠償金を支払ったことを証明するための書類です。被害者に署名・捺印してもらった「領収書」や、銀行の「振込明細書」などがこれにあたります。「誰が、誰に、いつ、いくら支払ったか」が明確にわかるものを用意しましょう。
損害の種類に応じて必要になる書類
被害者が受けた損害の種類によって、共通書類に加えて以下の書類が必要になります。ご自身の状況に合わせて準備を進めてください。
傷害(ケガ)に関する損害の書類
被害者がケガをした場合の、治療費や休業による減収などを請求するために必要な書類です。
| 書類名 | 主な内容と入手先 |
|---|---|
| 診断書 | ケガの部位や程度、治療にかかる期間などが記載された書類です。治療を受けた病院で作成を依頼します。 |
| 診療報酬明細書 | 治療内容や投薬、検査などの詳細な医療費の内訳がわかる書類です。治療を受けた病院から取り寄せます。 |
| 休業損害証明書 | 事故によるケガが原因で仕事を休み、収入が減少したことを証明する書類です。勤務先に作成を依頼します。 |
| 通院交通費明細書 | 病院への通院にかかった交通費(公共交通機関、タクシー、ガソリン代など)を証明する書類です。請求者自身で作成します。 |
後遺障害に関する損害の書類
ケガの治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に請求するための書類です。
| 書類名 | 主な内容と入手先 |
|---|---|
| 後遺障害診断書 | これ以上治療を続けても改善が見込めない状態(症状固定)になった後、残った後遺障害の内容について医師が作成する専門の診断書です。治療を受けた病院で作成を依頼します。 |
| レントゲン写真・MRI画像など | 後遺障害の状態を客観的に証明するための医用画像です。診断書を作成した病院から借用します。 |
死亡に関する損害の書類
残念ながら被害者がお亡くなりになった場合に、ご遺族(相続人)が請求するために必要な書類です。
| 書類名 | 主な内容と入手先 |
|---|---|
| 死亡診断書(または死体検案書) | 被害者の死亡を医学的に証明する書類です。病院または警察から交付されます。 |
| 戸籍謄本(除籍謄本) | 被害者の死亡の事実と、請求者が正当な相続人であることを証明するために必要です。被害者の本籍地がある市区町村役場で取得します。 |
| 請求者(相続人)全員の印鑑証明書 | 相続人全員が請求に同意していることを証明するために必要です。各相続人がお住まいの市区町村役場で取得します。 |
ここに挙げた以外にも、事故の状況や損害の内容によっては追加の書類を求められることがあります。不明な点があれば、ためらわずに加入している自賠責保険会社に問い合わせましょう。
加害者請求で支払われる保険金の範囲と限度額
加害者が自賠責保険に請求する場合でも、支払われる保険金の範囲や上限額は、被害者が請求する場合と全く同じです。自賠責保険の保険金は、あくまでも交通事故の被害者を救済するためのものであり、その支払限度額は被害者1名ごとに定められています。
ここでは、損害の種類ごとに支払われる保険金の範囲と限度額を詳しく解説します。
傷害(ケガ)による損害(上限120万円)
交通事故によって被害者がケガをした場合に支払われる保険金で、被害者1名あたりの上限額は120万円です。治療費や通院交通費、休業による損害、慰謝料などがこの範囲に含まれます。具体的な内容は以下の通りです。
| 損害の種類 | 内容 |
|---|---|
| 治療関係費 | 診察料、入院費、手術費、薬代、柔道整復等の費用、通院交通費など |
| 休業損害 | ケガによって仕事ができず、収入が減少したことに対する補償(原則として1日あたり6,100円) |
| 慰謝料 | 事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償(1日あたり4,300円) |
これらの合計額が120万円を超える場合、超えた部分については自賠責保険からは支払われません。
後遺障害による損害(等級に応じて上限4000万円)
交通事故によるケガが完治せず、「症状固定」と診断された後に残った機能障害や神経症状などを後遺障害といいます。後遺障害による損害は、傷害による損害(上限120万円)とは別枠で支払われます。
後遺障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が認定され、その等級によって支払われる保険金の上限額が変わります。損害の内容には、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する「慰謝料」と、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する「逸失利益」が含まれます。
| 後遺障害等級 | 保険金限度額 | 後遺障害の例 |
|---|---|---|
| 【別表第1】 第1級(要介護) | 4,000万円 | 神経系統の機能や精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 【別表第2】 第1級 | 3,000万円 | 両眼が失明したもの、そしゃく・言語の機能を完全に失ったものなど |
| 第7級 | 1,051万円 | 1手の親指を含む3の手指を失ったもの、1足のリスフラン関節以上を失ったものなど |
| 第12級 | 224万円 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害・運動障害を残すもの、局部に頑固な神経症状を残すものなど |
| 第14級 | 75万円 | 局部に神経症状を残すもの(むちうちなど) |
※上記はあくまで一例です。等級の認定は、損害保険料率算出機構が専門的かつ中立な立場から行います。
死亡による損害(上限3000万円)
残念ながら被害者が交通事故によって死亡した場合に支払われる保険金で、被害者1名あたりの上限額は3000万円です。葬儀費や、被害者が生きていれば将来得られたはずの収入(逸失利益)、そして被害者本人および遺族の慰謝料が含まれます。
| 損害の種類 | 内容・金額 |
|---|---|
| 葬儀費 | 原則100万円 |
| 逸失利益 | 死亡によって失われた、将来得られたはずの収入。被害者の年齢、収入、家族構成などから算出される。 |
| 死亡本人への慰謝料 | 400万円 |
| 遺族への慰謝料 | 請求権者(配偶者、子、父母)の人数によって変動。 ・1名:550万円 ・2名:650万円 ・3名以上:750万円 ※被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算される。 |
これらの損害額の合計が、3000万円を上限として支払われます。
より詳細な支払基準については、国土交通省のウェブサイトで確認できます。
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省
自賠責保険の加害者請求を行う際の注意点とQ&A
自賠責保険の加害者請求は、手続きが複雑で分かりにくい点も少なくありません。ここでは、請求手続きを進めるにあたって特に注意すべきポイントや、よくある質問について分かりやすく解説します。
請求権の時効に注意する
自賠責保険の加害者請求には「時効」があり、期限を過ぎると請求する権利がなくなってしまいます。必ず時効の期間を把握しておきましょう。
加害者請求の時効は、加害者が被害者に対して賠償金を支払った日の翌日から3年です。
交通事故が発生した日の翌日から3年で時効となる「被害者請求」とは、時効のカウントが始まるタイミング(起算点)が異なりますので注意が必要です。被害者との示談交渉が長引いた場合でも、ご自身が賠償金を支払った日から計算されることを覚えておきましょう。
加害者に重過失があると保険金が減額される
交通事故の原因が、加害者の重大な過失(重過失)によるものである場合、自賠責保険から支払われる保険金が減額されることがあります。これを「重過失減額」といいます。
主な重過失の例と減額割合は以下の通りです。
| 損害の種類 | 減額割合 | 重過失の内容 |
|---|---|---|
| 傷害による損害 | 20% | 無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転、ひき逃げ など |
| 後遺障害または死亡による損害 | 20%または30% |
例えば、酒酔い運転で事故を起こし、被害者に治療費として100万円を支払った場合、加害者請求で受け取れる保険金は20%減額された80万円となります。詳細な減額割合については、国土交通省のウェブサイトでも確認できます。
請求から支払いまでの期間はどれくらい?
自賠責保険会社に請求書類を提出してから、保険金が支払われるまでの期間は、事案によって異なります。
一般的には、書類に不備がなくスムーズに手続きが進んだ場合で、1ヶ月~2ヶ月程度が目安とされています。ただし、後遺障害の等級認定が必要な場合や、事故状況の調査に時間がかかる複雑なケースでは、半年以上かかることもあります。
書類の不備があると、その分支払いまでの期間が長引いてしまうため、提出前には念入りに確認することが大切です。
手続きが複雑な場合は専門家への相談も検討
加害者請求は、被害者請求に比べて手続きが複雑で、必要書類も多岐にわたります。もし、ご自身での手続きに不安を感じたり、被害者との示談交渉が難航したりしている場合は、専門家への相談も有効な選択肢です。
主な相談先としては、弁護士や行政書士が挙げられます。
- 弁護士
書類作成や請求手続きの代行はもちろん、被害者との示談交渉や、万が一裁判になった場合の対応まで依頼できます。特に、過失割合などで被害者と意見が対立している場合に頼りになります。 - 行政書士
煩雑な請求書類の作成や収集、保険会社への提出代行を依頼できます。法的な紛争には介入できませんが、手続きをスムーズに進めたい場合に適しています。
専門家に依頼すると費用はかかりますが、手続きにかかる時間や手間を大幅に削減できるだけでなく、適正な保険金を確実に受け取れる可能性が高まるというメリットがあります。
まとめ
本記事では、自賠責保険の加害者請求について、手続きの流れや必要書類、注意点を詳しく解説しました。
加害者請求は、被害者に支払った賠償金を自賠責保険から回収するための重要な制度です。示談成立後に必要書類を揃えて請求しますが、請求権には時効があるため迅速な対応が求められます。
手続きが複雑な場合や重過失が問われるケースでは、弁護士など専門家へ相談することで、スムーズかつ適切な保険金請求が可能になるでしょう。
仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください
仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。
お気軽にご相談、ご予約ください。