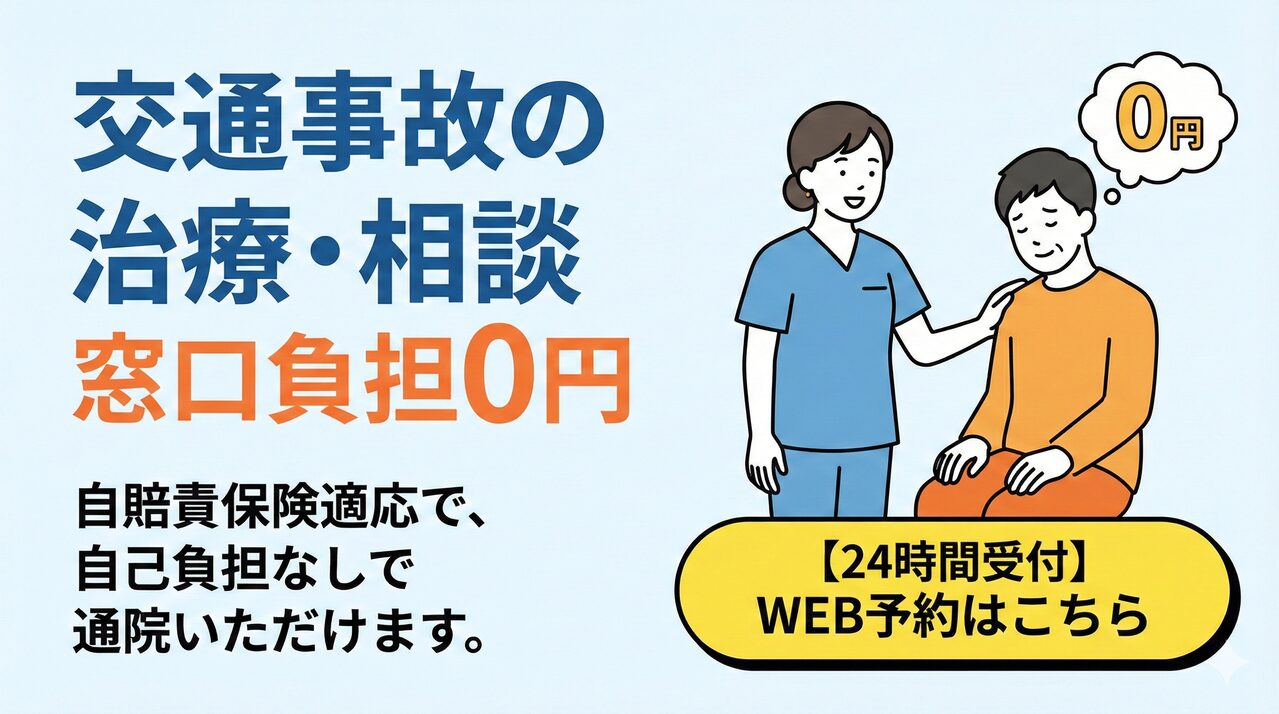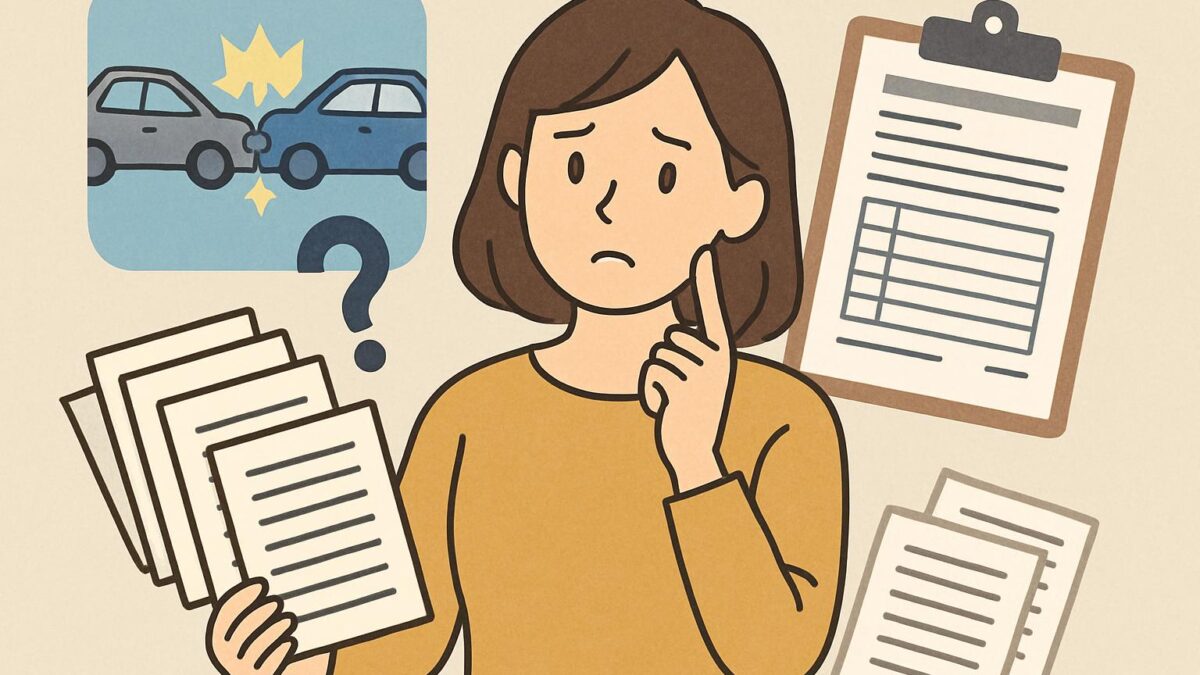交通事故の加害者が任意保険に未加入でも、自賠責保険に直接請求できる「被害者請求」。しかし、手続きが複雑で必要書類も多岐にわたります。
被害者請求に必要な書類を一覧でわかりやすく解説
各書類の入手方法から提出までの流れ、注意点まで網羅しているため、この記事を読めば迷わず手続きを進められます。書類集めが難しい場合は弁護士への相談も有効です。
自賠責保険の被害者請求とは?加害者請求との違い
交通事故に遭ってしまったとき、ケガの治療費や仕事を休んだ分の補償などを「自賠責保険」に請求できます。この請求方法には、被害者が直接手続きを行う「被害者請求」と、加害者が手続きを行う「加害者請求」の2種類があります。まずは、それぞれの特徴と違いを理解しておきましょう。
被害者請求とは|交通事故の被害者が直接保険金を請求する方法
被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、損害賠償額(治療費や慰謝料など)を直接請求する手続きのことです。この制度は、被害者を保護するために自動車損害賠償保障法で認められている権利です。
通常、損害賠償は加害者との示談交渉が成立してから支払われますが、被害者請求では示談成立前でも請求が可能です。そのため、「加害者が賠償金の支払いに応じてくれない」「示談交渉が長引いているが、当面の治療費を確保したい」といった場合に、被害者にとって非常に重要な手続きとなります。
被害者自身が必要書類を集めて手続きを進めるため手間はかかりますが、加害者の対応に左右されず、ご自身のタイミングで請求できるのが大きなメリットです。
加害者請求とは|加害者が立て替えた賠償金を請求する方法
加害者請求とは、交通事故の加害者が、まず被害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償金を支払い、その後に自身が加入している自賠責保険会社に対して、支払った金額の範囲内で保険金を請求する手続きです。
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が示談交渉から賠償金の支払いまでを代行し、その中で自賠責保険への請求手続きも一括して行う「一括対応」が一般的です。そのため、多くの交通事故ではこの加害者請求の形で処理が進められています。
被害者請求と加害者請求の主な違い
被害者請求と加害者請求の主な違いを以下の表にまとめました。どちらの方法で請求するかによって、請求者や手続きのタイミングが大きく異なります。
| 項目 | 被害者請求 | 加害者請求 |
|---|---|---|
| 請求する人 | 交通事故の被害者 | 交通事故の加害者 |
| 請求のタイミング | 加害者との示談成立前でも可能 | 原則として、加害者が被害者に賠償金を支払った後 |
| 請求先 | 加害車両の自賠責保険会社 | |
| 必要書類の収集 | 被害者が主体となって集める | 加害者が主体となって集める(被害者の協力が必要) |
| メリット | ・加害者の対応に関わらず請求できる ・示談成立前に保険金を受け取れる可能性がある ・賠償額の透明性が高い | ・(加害者にとって)支払った賠償金を保険で回収できる ・(被害者にとって)任意保険会社が対応すれば手続きの手間が少ない |
自賠責保険の請求手続きについて、より詳しい公的な情報は国土交通省の自賠責保険ポータルサイトでも確認できます。
一目でわかる自賠責保険の被害者請求で必要な書類一覧
自賠責保険の被害者請求では、損害の内容にかかわらず共通して必要な書類と、損害の種類(傷害・後遺障害・死亡)に応じて追加で必要となる書類があります。ここでは、それぞれを一覧でわかりやすく解説します。ご自身の状況に合わせて、どの書類が必要になるかを確認しましょう。
なお、具体的な書式や詳細については、請求先となる加害者の自賠責保険会社にご確認ください。
必ず提出が必要な基本書類
どのような損害を請求する場合でも、共通して提出が必要となる基本的な書類です。まずはこれらの書類を準備することから始めましょう。
| 書類名 | 簡単な説明 |
|---|---|
| 保険金(共済金)支払請求書 | 請求者の情報や振込先口座などを記入する、請求の核となる書類です。保険会社から取り寄せます。 |
| 交通事故証明書 | 交通事故があった事実を公的に証明する書類です。自動車安全運転センターで発行されます。 |
| 事故発生状況報告書 | 事故の発生状況を図や文章で説明するための書類です。保険会社から取り寄せます。 |
| 請求者の印鑑証明書 | 請求書に押印した実印が本人のものであることを証明する書類です。市区町村役場で取得します。 |
| 委任状・代理人の印鑑証明書 | 弁護士など代理人が請求手続きを行う場合に必要です。 |
| 示談書(※示談が成立している場合) | 加害者との間で示談が成立している場合に、その内容を証明するために提出します。 |
損害の内容に応じて必要となる書類
ここからは、基本書類に加えて、請求する損害の内容に応じて必要となる書類を解説します。
傷害(ケガ)による損害を請求する場合の必要書類
交通事故によるケガの治療費や、それに伴う休業損害などを請求する場合に必要な書類です。
| 書類名 | 簡単な説明 |
|---|---|
| 診断書 | ケガの部位や程度、治療期間などを医師に証明してもらう書類です。 |
| 診療報酬明細書 | 治療にかかった費用の内訳が記載された書類です。病院や薬局で発行されます。 |
| 施術証明書・施術費明細書 | 診療報酬明細書の接骨院バージョンです。 |
| 通院交通費明細書 | 通院にかかった交通費(公共交通機関、ガソリン代など)を証明する書類です。 |
| 休業損害証明書 | ケガのために仕事を休んだことによる減収を証明する書類です。勤務先に作成を依頼します。 |
後遺障害による損害を請求する場合の必要書類
治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に、傷害による損害に加えて請求する際に必要な書類です。
| 書類名 | 簡単な説明 |
|---|---|
| 後遺障害診断書 | 後遺障害の内容や程度について、医師に作成してもらう専用の診断書です。 |
| レントゲン写真・MRI画像など | 後遺障害の状態を客観的に証明するために、必要に応じて提出します。 |
死亡による損害を請求する場合の必要書類
残念ながら被害者の方がお亡くなりになった場合に、ご遺族(損害賠償請求権者)が請求する際に必要な書類です。
| 書類名 | 簡単な説明 |
|---|---|
| 死亡診断書または死体検案書 | 被害者が亡くなったことを証明する公的な書類です。 |
| 戸籍謄本(または除籍謄本) | 被害者の死亡の事実と、相続関係を証明するために必要です。 |
| 請求者全員の戸籍謄本 | 損害賠償請求権を持つ相続人全員の現在の戸籍を証明する書類です。 |
| 請求者全員の印鑑証明書 | 請求者が複数いる場合は、全員分の印鑑証明書が必要になります。 |
自賠責の被害者請求で使う各必要書類の入手方法
自賠責保険の被害者請求で必要となる書類は、それぞれ入手先が異なります。保険会社から取り寄せるもの、ご自身で役所や病院へ足を運んで取得するものなど様々です。ここでは、各書類をどこで、どのように入手すればよいのかを分かりやすく解説します。
保険会社から取り寄せる書類
請求手続きの中心となる書類は、加害者が加入している自賠責保険会社から直接取り寄せます。まず「交通事故証明書」で加害者の自賠責保険会社名を確認し、その保険会社の事故受付窓口へ連絡しましょう。「被害者請求をしたい」と伝えれば、必要な書類一式を送付してくれます。
| 主な書類名 | 入手先 | 補足 |
|---|---|---|
| 保険金支払請求書(兼 同意書) | 加害者の自賠責保険会社 | 請求の意思を示す最も重要な書類です。請求者本人の署名・捺印が必要です。 |
| 事故発生状況報告書 | 加害者の自賠責保険会社 | 事故の状況を図や文章で説明する書類です。記憶が鮮明なうちに作成しましょう。 |
病院や薬局・接骨院で発行してもらう書類
ケガの治療に関する損害を証明するため、通院した医療機関や薬局、接骨院で書類を発行してもらう必要があります。受付窓口で「自賠責保険の被害者請求で使うので、診断書(または診療報酬明細書)を発行してください」と依頼してください。発行には数日から数週間かかる場合があり、文書作成料も必要です。
| 主な書類名 | 入手先 | 補足 |
|---|---|---|
| 診断書 | 治療を受けた病院・クリニック | ケガの部位や治療期間などが記載されます。 |
| 診療報酬明細書 | 治療を受けた病院・クリニック | 治療内容と費用の詳細が記載された明細書です。 |
| 施術証明書・施術費明細書 | 施術を受けた接骨院 | 施術内容と費用の詳細が記載された明細書です。 |
| 後遺障害診断書 | 症状固定の診断をした医師 | 後遺障害等級認定を申請する場合に必須です。医師に正確な記載を依頼することが重要です。 |
| 薬局の領収書 | 薬を処方された薬局 | 処方された薬代を証明します。紛失しないように保管しておきましょう。 |
勤務先に作成してもらう書類
交通事故によるケガが原因で仕事を休み、給与が減ってしまった損害(休業損害)を請求する場合には、勤務先に証明書を作成してもらう必要があります。会社の経理担当者や人事担当者に事情を説明し、「休業損害証明書」の作成を依頼しましょう。自賠責保険会社から取り寄せた所定の用紙に、休んだ日や事故前の給与額などを正確に記入してもらいます。
警察署や関係機関で入手する書類
交通事故があったことを公的に証明する「交通事故証明書」は、被害者請求において必須の書類です。事故を届け出た警察署を管轄する「自動車安全運転センター」で発行されます。警察署や交番に備え付けの申請用紙を使って郵便局で申し込むか、センターの窓口で直接申請することで入手できます。オンラインでの申請も可能です。
詳しくは、自動車安全運転センターのウェブサイトをご確認ください。
市区町村役場で取得する書類
請求者本人であることを証明するためや、損害の内容によっては、お住まいの市区町村役場で公的な書類を取得する必要があります。窓口で申請するほか、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機で取得できる場合もあります。
| 主な書類名 | 入手先 | 補足 |
|---|---|---|
| 印鑑証明書 | 住民票のある市区町村役場 | 請求書に押印した実印が本人のものであることを証明します。発行から3ヶ月以内など有効期間に注意が必要です。 |
| 住民票 | 住民票のある市区町村役場 | 慰謝料の算定などで必要となる場合があります。 |
| 戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村役場 | 死亡事故の際に、被害者と請求者(相続人)の関係を証明するために必要です。 |
被害者請求の必要書類を提出するまでの流れ
交通事故の被害者になってしまった場合、自賠責保険への被害者請求はどのような手順で進むのでしょうか。ここでは、事故発生から保険金が支払われるまでの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。全体像を把握しておくことで、落ち着いて手続きを進められるようになります。
【手順1】交通事故の発生と加害者情報の確認
すべての手続きは、交通事故の発生から始まります。事故に遭ったら、まずは警察に必ず連絡してください。警察に届け出ることで、後の請求に必要となる「交通事故証明書」が発行されるようになります。同時に、ご自身の安全を確保し、必要であれば救急車を呼びましょう。
そして、加害者の情報を正確に確認しておくことが非常に重要です。以下の項目は、その場でメモを取るか、スマートフォンのカメラで撮影するなどして記録しておきましょう。
- 加害者の氏名、住所、連絡先
- 加害車両のナンバープレート(登録番号)
- 加害者が加入している自賠責保険の保険会社名と証明書番号
これらの情報は、被害者請求を行う際に加害者の自賠責保険会社を特定するために不可欠です。
【手順2】治療と必要書類の準備
事故によるケガの治療は、医師の指示に従って継続してください。痛みが軽いからといって自己判断で通院をやめてしまうと、後から症状が悪化した場合に事故との因果関係を証明するのが難しくなります。治療に専念することが、適切な補償を受けるための第一歩です。
治療と並行して、被害者請求に必要な書類の準備を始めましょう。前の章で解説したように、書類には病院で発行してもらう診断書や診療報酬明細書、役所で取得する印鑑証明書など、さまざまな種類があります。書類によっては発行に時間がかかるものもあるため、早めに準備に着手することをおすすめします。
【手順3】加害者の自賠責保険会社へ書類一式を提出
必要な書類がすべて揃ったら、加害者が加入している自賠責保険会社へ提出します。まずは相手方保険会社の事故受付窓口に連絡し、「被害者請求を行いたい」と伝えてください。そうすると、保険会社から請求に必要な書類一式(保険金請求書など)が送られてきます。
送られてきた請求書に必要事項を記入し、ご自身で準備した他の書類とあわせて、保険会社に郵送で提出するのが一般的です。提出する前には、必ずすべての書類のコピーを取り、手元に保管しておくようにしましょう。万が一の郵送事故や、後で内容を確認したい場合に役立ちます。
【手順4】損害保険料率算出機構による調査
自賠責保険会社が被害者から請求書類を受け取ると、その書類は「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という中立・公正な専門機関に送られます。
この機関では、提出された書類に基づいて、事故の状況、発生した損害の内容、後遺障害の等級などを客観的に調査します。この調査は、適正な保険金の支払いを実現するために非常に重要なプロセスです。調査には通常1か月から数か月程度の時間がかかります。
【手順5】保険金の支払い
損害保険料率算出機構による調査が完了すると、その結果が自賠責保険会社に報告されます。保険会社は、その調査結果を基に、支払うべき保険金の額を最終的に決定します。
支払額が決定されると、保険会社から被害者に対して支払額やその内訳が記載された通知書が送付され、その後、あらかじめ指定した銀行口座に保険金が振り込まれます。これで、被害者請求の一連の手続きは完了となります。
被害者請求で必要書類を準備するときの注意点
自賠責保険の被害者請求では、多くの書類を正確に準備する必要があります。ここでは、書類を準備する際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。スムーズに手続きを進めるために、必ず確認しておきましょう。
請求には時効がある
自賠責保険の被害者請求には「時効」があり、期限を過ぎると請求する権利がなくなってしまいます。損害の種類によって時効の起算日(時効期間のカウントが始まる日)が異なるため、注意が必要です。
| 損害の種類 | 時効期間 | 時効の起算日 |
|---|---|---|
| 傷害(ケガ)による損害 | 事故の翌日から3年 | 交通事故が発生した日の翌日 |
| 後遺障害による損害 | 症状固定日の翌日から3年 | これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した日(症状固定日)の翌日 |
| 死亡による損害 | 死亡日の翌日から3年 | 被害者が死亡した日の翌日 |
※2010年4月1日より前に発生した事故の場合、時効は2年となります。
時効が迫っている場合は、時効の完成を一時的に止める「時効の更新(中断)」という手続きが必要です。時効が心配な方は、早めに保険会社や弁護士などの専門家に相談しましょう。
後遺障害等級認定を正しく受けることが重要
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、損害保険料率算出機構によって「後遺障害等級」が認定されます。この等級(最も重い1級から14級まで)に応じて、受け取れる保険金の金額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが非常に重要です。
適切な等級認定を受けるためには、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の内容がカギとなります。ご自身の症状を正確に医師に伝え、具体的な症状や検査結果などを詳細に記載してもらうようにしましょう。
もし、認定された等級に納得できない場合は、「異議申立て」を行って再審査を求めることも可能です。後遺障害等級認定は専門的な知識が必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
書類に不備があると手続きが遅れる
提出した書類に不備(記入漏れ、記載内容の矛盾、必要書類の不足など)があると、保険会社から書類の訂正や追加提出を求められます。その分、損害調査が中断してしまい、保険金が支払われるまでの期間が大幅に長引いてしまう可能性があります。
特に、複数の書類に記載する事故日や氏名、住所などの情報が異なっていると、事実確認に時間がかかってしまいます。書類を提出する前には、以下の点を入念にチェックしましょう。
- すべての書類が揃っているか
- 氏名、住所、日付などに間違いや記入漏れはないか
- 各書類の記載内容に矛盾はないか
- 印鑑の押し忘れはないか
また、提出する書類はすべてコピーを取り、手元に控えとして保管しておくことが大切です。万が一、書類が紛失した場合や、後から内容を確認したくなった場合に役立ちます。
自賠責の必要書類集めや手続きが難しいときは弁護士へ相談
自賠責保険の被害者請求は、必要書類の種類が多く、手続きも複雑です。特に、お仕事をしながら治療を続けている方や、ご家族が被害に遭われた方にとって、すべての手続きを自分で行うのは大きな負担となります。また、後遺障害が残るような大きな事故の場合、専門知識がなければ適正な賠償金を受け取れない可能性もあります。
もし、書類集めや手続きに少しでも不安や難しさを感じたら、交通事故問題の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に被害者請求を依頼するメリット
弁護士に被害者請求を依頼すると、被害者の方には次のような多くのメリットがあります。これにより、被害者ご本人は治療に専念しやすくなります。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 面倒な手続きを一任できる | 必要書類の収集・作成から保険会社とのやり取りまで、複雑な手続きをすべて代行してもらえます。 |
| 適正な後遺障害等級認定の可能性が高まる | 後遺障害診断書の内容を法的な観点からチェックし、適切な等級認定を得るためのアドバイスやサポートを受けられます。 |
| 賠償金の増額が期待できる | 自賠責保険の基準よりも高額な「弁護士基準(裁判基準)」を用いて交渉するため、慰謝料などの賠償額が増える可能性があります。 |
| 精神的な負担が軽くなる | 加害者側の保険会社との交渉窓口になってもらえるため、直接やり取りするストレスから解放されます。 |
弁護士費用特約が利用できないか確認する
弁護士に依頼するときの費用が心配な方も多いかもしれません。しかし、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性があります。年額数千円で加入できるコスパ抜群の特約です。もし入っていないなら、次回の自動車保険更新時に必ず加入しましょう。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際に、弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が負担してくれる制度です。多くの場合、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までが上限となっており、ほとんどのケースで自己負担は発生しません。
この特約を利用しても、自動車保険の等級が下がることはありませんので、ご自身の保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせてみましょう。もし特約がなくても、初回相談を無料で行っている法律事務所は多くあります。当院でもご紹介できますのでご相談下さい。
まとめ
自賠責保険の被害者請求では、損害の内容に応じて多岐にわたる書類が必要です。本記事で解説した一覧や入手方法を参考に、漏れなく準備を進めましょう。
請求には時効があり、特に後遺障害等級が適切に認定されるかは、受け取れる保険金額を左右する重要なポイントです。書類の準備や手続きに少しでも不安を感じる場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください
仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。
お気軽にご相談、ご予約ください。