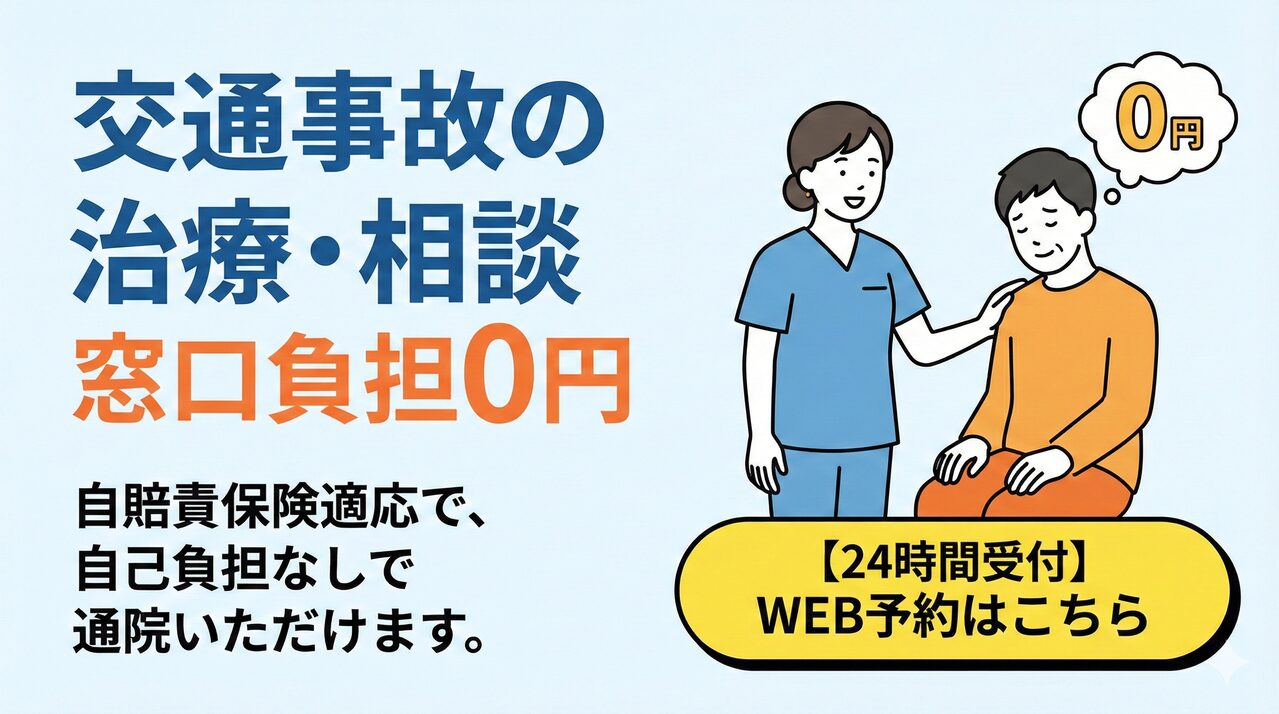交通事故で接骨院に通院する際、「慰謝料は一日いくらもらえるの?」と不安ですよね。
この記事を読めば、慰謝料の算定基準によって金額が大きく変わる事実と、各基準での1日あたりの目安、計算方法、請求時の注意点、増額のコツまで具体的に分かります。納得のいく慰謝料請求に必要な知識が全て手に入ります。
交通事故の慰謝料とは? まず知っておきたい基本
交通事故に遭ってしまうと、身体的なダメージだけでなく、精神的な苦痛も伴います。この精神的苦痛に対して支払われるのが「慰謝料」です。しかし、慰謝料にはいくつかの種類があり、それぞれ意味合いが異なります。
また、「接骨院での治療も慰謝料の対象になるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。この章では、交通事故における慰謝料の基本的な知識について、わかりやすく解説します。
慰謝料の種類とそれぞれの意味
交通事故の慰謝料は、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。その苦痛の内容に応じて、主に以下の3つの種類に分けられます。それぞれの意味を正しく理解しておきましょう。
| 慰謝料の種類 | どのような場合に支払われるか |
|---|---|
| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 交通事故による怪我の治療のために入院や通院をしたことによる精神的苦痛に対して |
| 後遺障害慰謝料 | 治療を続けても怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対して |
| 死亡慰謝料 | 交通事故により被害者が亡くなられた場合の、ご本人およびご遺族の精神的苦痛に対して |
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料とも呼ばれます)は、交通事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされたことによって生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
例えば、骨折して手術や入院が必要になったり、むちうちで長期間通院したりする場合などが該当します。この慰謝料の金額は、原則として治療にかかった期間や実際の通院日数などをもとに算定されます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が治療を続けても完治せず、身体的または精神的な機能障害(後遺障害)が残ってしまった場合に、そのことによって生じる将来にわたる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料を受け取るためには、自賠責保険の基準に基づく後遺障害等級の認定を受ける必要があります。等級は症状の重さによって1級から14級までに区分され、等級が高い(症状が重い)ほど慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者の方が残念ながらお亡くなりになった場合に、亡くなられた被害者ご本人の無念さや精神的苦痛、そしてご遺族(配偶者、子、父母など)が被る精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
この慰謝料には、亡くなった被害者本人に対する慰謝料と、近親者固有の慰謝料が含まれることがあります。金額は、被害者の家庭内での立場(一家の支柱であったかなど)や、扶養家族の有無などによって変動します。
接骨院での治療も慰謝料の対象になる?
交通事故で怪我をした際、整形外科などの病院だけでなく、接骨院(整骨院とも呼ばれます)で治療を受けるケースも少なくありません。では、接骨院での施術費用や、それに基づく入通院慰謝料は認められるのでしょうか。
結論から申し上げますと、医師の指示や同意があった場合など、施術の必要性・相当性が認められれば、接骨院での施術も入通院慰謝料の対象となるのが原則です。
ただし、漫然とした長期の施術や、症状改善が見られない場合の施術などは、必要性・相当性が否定され、慰謝料の算定基礎となる治療期間として認められない場合や、施術費用そのものが支払われない可能性もあるため注意が必要です。
接骨院通院での慰謝料は一日いくら? 金額の目安を解説
交通事故で怪我をして接骨院に通院した場合、加害者側の保険会社から支払われる慰謝料は、一体一日あたりいくらくらいになるのでしょうか。
この章では、慰謝料の金額を計算する際の基準や、それぞれの基準における一日あたりの金額の目安、そして計算方法について、わかりやすく解説していきます。
慰謝料の算定基準は3つある
交通事故の慰謝料を計算する際には、主に以下の3つの基準が用いられます。どの基準で計算するかによって、最終的に受け取れる慰謝料の金額が大きく変わってくることがありますので、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
自賠責保険基準
自賠責保険基準は、自動車やバイクを運転する際に法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」で用いられる基準です。
交通事故の被害者を最低限救済することを目的としており、慰謝料の支払い基準も法令で明確に定められています。3つの基準の中では、最も金額が低くなります。
任意保険基準
任意保険基準は、加害者が任意で加入している自動車保険会社が、慰謝料を支払う際に用いる独自の基準です。
各保険会社がそれぞれ内部的に基準を設けており、その具体的な内容は公表されていません。「自賠責保険基準よりは高く、後述する弁護士基準(裁判基準)よりは低い金額となることが多い」と説明されることが多いのですが、接骨院の現場にいる経験では、自賠責基準と同額で提示されることが大半です。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は、過去の交通事故に関する裁判例(判例)を基にして作られた基準で、「裁判基準」とも呼ばれます。
弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する場合や、実際に裁判になった場合に用いられる基準です。3つの基準の中では最も正当な金額であり、慰謝料額が最も高額になる可能性が高いとされています。
【早わかり】基準別 一日あたりの慰謝料の目安
それでは、具体的に一日あたりいくらくらいの慰謝料が見込めるのでしょうか。
ここでは、特に金額の目安が示しやすい「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」について、その計算方法と金額の目安を見ていきましょう。任意保険基準については、保険会社ごとに異なり非公開のため、ここでは割愛します。
自賠責保険基準の場合の計算方法と金額
自賠責保険基準における入通院慰謝料は、原則として1日あたり4,300円です(2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合。それ以前の事故は4,200円)。この日額に、以下のいずれか「少ない方」の日数を乗じて慰謝料額を計算します。
- 総治療期間(事故日から治療終了日または症状固定日までの全日数)
- 実治療日数(実際に入院や通院をした日数)の2倍
例えば、総治療期間が90日(約3ヶ月)で、実際に接骨院に通った日数が40日だった場合、「実治療日数の2倍(40日×2=80日)」の方が「総治療期間(90日)」よりも少ないため、80日を基礎として計算します。
この場合の慰謝料は、4,300円 × 80日 = 344,000円となります。
ただし、自賠責保険から支払われる傷害部分の保険金(治療費、休業損害、慰謝料など全てを含む)には、上限120万円という総額の限度がありますので注意が必要です。
弁護士基準の場合の計算方法と金額
弁護士基準(裁判基準)では、自賠責保険基準のような「一日いくら」という単純な日額計算ではなく、入通院した期間に応じて慰謝料の相場が定められた算定表(通称「赤い本」や「青本」に掲載されている:当センターの刊行物について(青本及び赤い本) – 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター)を基に金額が算定されます。
この算定表は、むちうち症などの比較的軽傷の場合(「別表Ⅱ」などと呼ばれる表)と、それ以外の骨折などの傷害の場合(「別表Ⅰ」などと呼ばれる表)で、それぞれ異なる基準が設けられています。
そのため、「一日あたりいくら」と固定されているわけではありませんが、一般的に自賠責保険基準よりも高額になる傾向があります。
参考として、弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料の目安(むちうち等で他覚所見がない場合など、比較的軽傷の場合)を以下に示します。実際の請求額は、個別の怪我の状況や通院頻度、弁護士との相談により異なります。
| 通院期間 | 慰謝料の目安(むちうち等軽傷用) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 |
※上記の表はあくまで目安です。骨折などの他覚所見がある重傷の場合は、これよりも高額な基準(別表Ⅰ)が適用されることが一般的です。
通院日数と治療期間 どちらが重要?
慰謝料を算定する上で、「実際に通院した日数(実治療日数)」と「治療にかかった全体の期間(治療期間)」のどちらがより重要視されるかは、用いる算定基準によって考え方が異なります。
自賠責保険基準では、前述の通り「総治療期間」と「実治療日数の2倍」を比較し、少ない方の日数を採用して計算します。
そのため、治療期間が長くても実治療日数が極端に少ない場合(例:3ヶ月間で5日しか通院しなかったなど)は、慰謝料が低くなります。逆に、短期間に集中して通院した場合でも、治療期間が短いと、そちらが基準になることもあります。つまり、両者のバランスが考慮されます。
一方、弁護士基準(裁判基準)では、主に「治療期間」を基礎として、算定表に基づいて慰謝料を算定します。
ただし、治療期間が長くても、通院頻度が著しく低い場合(例えば、月に1~2回程度の通院が漫然と続いているようなケース)は、症状が軽微である、あるいは治療の必要性が低いと判断され、慰謝料が減額調整される可能性があります。適切な頻度での継続的な通院が、治療の必要性を示す上で重要になります。
したがって、どちらか一方だけが重要というわけではなく、ご自身の怪我の症状や治療内容に応じて、医師や柔道整復師の指示に従い、適切な期間、適切な頻度で通院することが、最終的に適正な慰謝料を受け取るためには大切です。
交通事故で接骨院に通う場合の慰謝料計算シミュレーション
ここでは、実際に交通事故で接骨院に通院した場合、慰謝料がいくらになるのか、具体的なケースを想定してシミュレーションしてみましょう。
前章で解説した「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」のそれぞれで計算します。
【ケース1】通院期間90日 通院実日数45日の場合
まず、治療期間が90日(約3ヶ月)、そのうち実際に接骨院に通った日数が45日だったケースを考えてみましょう。
自賠責保険基準での計算
自賠責保険基準では、慰謝料は1日あたり4,300円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)で計算されます。対象となる日数は、「治療期間」と「実治療日数 × 2」のうち、少ない方の日数が採用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療期間 | 90日(約3ヶ月) |
| 実治療日数 | 45日 |
| 実治療日数 × 2 | 45日 × 2 = 90日 |
| 慰謝料の対象となる日数 | 90日(「治療期間90日」と「実治療日数×2の90日」の少ない方) |
| 慰謝料額(自賠責保険基準) | 4,300円 × 90日 = 387,000円 |
感の良い方はお気づきでしょう。2日に1回ペースで通院すると、自賠責保険での慰謝料は最大になります。これ以上のペースで通院しても増額することはありませんが、より少ないペースだと減額します。
弁護士基準(裁判基準)での計算
弁護士基準(裁判基準)では、専用の算定表(入通院慰謝料基準表)を用いて慰謝料を計算します。
むちうちなど、比較的軽傷の場合に使われる「別表Ⅱ」を参考にすると、以下のようになります。ただし、これはあくまで目安であり、怪我の状況や通院頻度によって金額が変動することがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通院期間 | 3ヶ月 |
| 慰謝料額(弁護士基準・別表Ⅱの目安) | 約53万円 |
このように、同じ通院状況でも、自賠責保険基準と弁護士基準では慰謝料額に差が出ることがわかります。
【ケース2】通院期間180日 通院実日数90日の場合
次に、治療期間が180日(約6ヶ月)、そのうち実際に接骨院に通った日数が90日だったケースでシミュレーションしてみましょう。
自賠責保険基準での計算
計算方法はケース1と同様です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療期間 | 180日(約6ヶ月) |
| 実治療日数 | 90日 |
| 実治療日数 × 2 | 90日 × 2 = 180日 |
| 慰謝料の対象となる日数 | 180日(「治療期間180日」と「実治療日数×2の180日」の少ない方) |
| 慰謝料額(自賠責保険基準) | 4,300円 × 180日 = 774,000円 |
これもさきほど同様、自賠責保険における最大額です。通院日数が少ないとこの例よりも低額になります。
弁護士基準(裁判基準)での計算
弁護士基準(裁判基準)の「別表Ⅱ」(むちうち等の場合)を参考にすると、以下のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通院期間 | 6ヶ月 |
| 慰謝料額(弁護士基準・別表Ⅱの目安) | 約89万円 |
このケースでも、弁護士基準の方が高額になります。
ただし、これらの金額はあくまで目安であり、個別の事情によって変動する可能性があることをご理解ください。より正確な金額を知りたい場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故で接骨院に通う際の慰謝料に関する注意点
交通事故の治療で接骨院に通院する場合、慰謝料を適切に受け取るためにはいくつかの注意点があります。これらを知っておくことで、後々のトラブルを避け、スムーズな解決につながります。
医師の同意を得てから接骨院へ通院する
交通事故で怪我を負った場合、まずは整形外科などの医師の診察を受けることが最優先です。
接骨院(整骨院)での施術を希望する場合でも、必ず事前に医師の診察を受け、接骨院への通院について同意、または指示を得るようにしましょう。
理由としては、診断や治療方針の決定は医師の専門領域であり、保険会社は医師の判断を重視するためです。
医師の許可なく接骨院に通院した場合、施術の必要性が認められず、保険会社が施術費や通院慰謝料を支払わないリスクがあります。必ず医師に相談し、その指示内容を保険会社にも伝えておくとスムーズです。
健康保険は使える? 交通事故治療を接骨院で受ける場合
交通事故の治療でも、接骨院で健康保険を使用することは原則として可能です。ただし、いくつかの注意点と手続きが必要です。立て替え払いや長期の治療になる可能性がある場合なら、自由診療は治療費が高額になる傾向があるため、健康保険の利用を検討しましょう。
健康保険を使用する主なメリットと手続きは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者側の過失割合が大きい場合に、自己負担額を抑えることができます。また、高額になりがちな自由診療を避けることで、保険会社との治療費に関する紛争リスクを低減できる場合があります。 |
| 手続き | 健康保険を使用する際は、ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。この手続きを怠ると、健康保険が使えない場合があります。詳細は全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトなどで確認しましょう。 |
| 注意点 | 接骨院によっては、交通事故の場合に健康保険の取り扱いをしない方針のところもありますので、事前に確認が必要です。また、労災保険が適用される業務中や通勤中の事故の場合は、健康保険ではなく労災保険が優先されます。 |
不明な点は、通院前に接骨院やご加入の健康保険組合に問い合わせることをお勧めします。
保険会社に接骨院への通院を事前に連絡する
医師の許可を得て接骨院に通院することになったら、加害者が加入している任意保険会社(または自賠責保険会社)に連絡を入れましょう。連絡を怠ると、後から施術費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定で不利になったりする可能性があります。
連絡する際には、以下の情報を伝えるとスムーズです。
- 医師から接骨院への通院許可を得たこと
- 通院する接骨院の名称と連絡先
- 通院を開始する予定日
保険会社によっては提携している接骨院を勧められることもありますが、ご自身で選んだ接骨院に通院して構いません。ただし、保険会社との良好な関係を保つためにも、事前の連絡と相談は重要です。
施術の必要性・相当性が認められない場合がある
接骨院での施術が、必ずしもすべて慰謝料の対象となるわけではありません。保険会社は、施術の「必要性」と「相当性」を独自に判断します。これらが認められない場合、その部分の施術費や慰謝料は支払われないことがあります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 怪我の症状と関係のない部位への施術
- 医学的に見て効果が期待できない長期間の漫然とした施術
- 医師の指示や診断内容と矛盾する施術
- あまりにも高額な施術
施術内容については、担当の柔道整復師とよく相談し、医師の診断内容と整合性を保ちながら、症状改善に必要な範囲で行うことが大切です。不明な点があれば、保険会社にも確認しましょう。
通院頻度が不適切だと慰謝料が減額される可能性
接骨院への通院頻度も、慰謝料額に影響を与える要素の一つです。通院頻度が極端に少ない場合、症状が軽微である、あるいは早期回復の意思がないと判断され、慰謝料が減額されることがあります。
逆に、毎日通院するなど過度な頻度での通院も施術の必要性が低いと見なされ、保険会社から治療費の支払いを早期に打ち切られたり、慰謝料算定で不利になったりする可能性があります。
適切な通院頻度は、怪我の症状や回復状況によって異なります。
医師や柔道整復師の指示に従い、症状改善に必要な範囲で、適切なペースで通院することが重要です。一般的には、事故直後の急性期はやや頻度が高く、症状の改善とともに徐々に頻度を減らしていくケースが多いです。
症状固定後の接骨院通院は原則対象外
「症状固定」とは、医学的にこれ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないと判断された状態を指します。症状固定と診断された日以降の接骨院への通院費用や、それに対する慰謝料は、原則として加害者側の保険会社からは支払われません。
症状固定の判断は、医師のみが行えます。もし症状固定後も痛みが続くなどの理由で通院を継続したい場合は、その費用は自己負担となる可能性が高いことを理解しておく必要があります。
ただし、例外的に症状固定後の施術が認められるケースもごく稀にありますが、保険会社との交渉が必要になります。
施術証明書や診断書をしっかり保管する
接骨院に通院した場合、慰謝料請求のためには「施術証明書」が必要になることがあります(通常の「一括対応」では不要)。
これは、いつからいつまで、どのような施術を何回受けたのかを証明する書類で、接骨院が発行します。また、医師から発行される「診断書」も、事故による怪我の内容や程度を証明するために非常に重要です。
これらの書類は、保険会社に提出を求められるだけでなく、万が一、後遺障害が残った場合の後遺障害等級認定の申請や、示談交渉、裁判になった場合にも重要な証拠となります。紛失しないように大切に保管し、必要に応じてコピーを取っておきましょう。
接骨院での慰謝料を増額させるためにできること
交通事故で接骨院に通院した場合、受け取れる慰謝料を少しでも増やすためには、いくつかのポイントがあります。
特に、交通事故問題に詳しい専門家である弁護士に相談することが、慰謝料増額への有効な手段となることがあります。
弁護士に相談するメリット
交通事故の慰謝料請求において、弁護士に相談・依頼することには、主に次のような大きなメリットがあります。これらのメリットを活かすことで、より適正な金額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
弁護士基準での請求が可能になる
慰謝料を計算する際には、主に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの基準が用いられます。
この中で、弁護士基準は過去の裁判例に基づいており、一般的に最も正当かつ高額な慰謝料が期待できる基準です。しかし、被害者ご自身が保険会社と交渉しても、弁護士基準での支払いに応じてもらうことは非常に難しいのが現実です。
弁護士が代理人として交渉することで、この弁護士基準、あるいはそれに近い金額での解決を目指すことが可能になり、結果として慰謝料の大幅な増額が期待できます。
保険会社との交渉を任せられる
交通事故の被害に遭うと、お体の治療に専念したいにもかかわらず、加害者側の保険会社の担当者と煩雑な交渉を行わなければなりません。
保険会社の担当者は交渉のプロです。被害者にとって有利な条件で示談を進めることは、当院の経験上ありません。
弁護士に依頼すれば、このような精神的な負担が大きい保険会社との交渉を全て任せることができます。弁護士は被害者の正当な権利を守るため、法的な根拠に基づいて適切な主張を行い、適正な慰謝料額の獲得を目指して交渉を進めます。
適切な後遺障害等級認定のサポート
交通事故による怪我が治療を続けても完治せず、残念ながら後遺症が残ってしまった場合、その後遺障害の程度に応じて「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来得られたはずの収入の補償)を請求できます。
この後遺障害等級は、その後の賠償額に非常に大きな影響を与えます。適切な等級認定を得るためには専門的な知識や、症状を正確に伝えるための資料の準備が不可欠で、被害者自身で用意するのは困難です。
弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の記載内容のチェックや、等級認定に必要な検査・資料収集に関するアドバイス、さらには認定結果に対する異議申し立ての手続きなど、適切な後遺障害等級認定を得るための手厚いサポートを受けることができます。
これにより、結果として受け取れる賠償金の増額につながる可能性が高まります。
交通事故に強い弁護士の選び方
慰謝料の増額や適正な賠償を受けるために弁護士に依頼する場合、交通事故の案件に精通し、実績のある弁護士を選ぶことが非常に重要です。弁護士にもそれぞれ専門分野があり、事務所によって年間の解決件数に大きな差があります。
以下のポイントを参考に、信頼できる弁護士を探しましょう。
| 選ぶ際のポイント | 確認すべき具体的な事項 |
|---|---|
| 交通事故案件の解決実績 | これまで取り扱ってきた交通事故案件の数(被害者側、加害者側)や、具体的な解決事例(特に接骨院通院のケース)を確認しましょう。当院でご紹介する弁護士事務所であれば安心できます。 |
| 医学的な知識の有無 | 後遺障害等級認定のサポートなど、医学的な知識が求められる場面も少なくありません。むちうちなどの症状や接骨院での施術内容についても理解がある弁護士が望ましいでしょう。 |
| 説明の分かりやすさと対応 | 法律や保険の専門用語を避け、相談者にとって分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるか、親身になって話を聞いてくれるかを確認しましょう。初回の相談などで相性を確かめることも大切です。 |
| 弁護士費用の明確さ | 相談料、着手金、報酬金といった弁護士費用の体系が明確に示されているかを確認しましょう。成功報酬の算定根拠なども事前にしっかり説明を受けることが重要です。 |
多くの法律事務所では交通事故に関する無料相談を実施しています。まずは複数の弁護士に実際に相談してみて、比較検討することをお勧めします。
弁護士費用特約の確認を忘れずに
弁護士に依頼する際に気になるのが弁護士費用ですが、ご自身やご家族が加入している自動車保険、火災保険、傷害保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士への相談料や依頼費用を保険で賄うことができます。
一般的に、弁護士費用特約を利用した場合の保険金の上限額は300万円程度、法律相談料の上限額は10万円程度と設定されていることが多いです。この特約を利用しても、翌年度以降の自動車保険料が上がることは基本的にありません(ノンフリート等級に影響しない場合がほとんどです)。
まずはご自身の保険契約内容をしっかりと確認し、弁護士費用特約の有無、利用条件、補償範囲などを把握しておきましょう。この特約があれば、費用の心配をせずに弁護士に依頼しやすくなり、慰謝料増額の可能性を追求する上で大きな助けとなります。
もし加入していないなら、次回更新の際に必ず加入しましょう。「弁護士費用特約」は、年間数千円で加入できる自動車保険においてコスパ最強の特約です。
交通事故で接骨院に通う慰謝料請求の流れ
交通事故に遭い、接骨院で治療を受けた場合、慰謝料などの損害賠償請求はどのような手順で進むのでしょうか。
ここでは、事故発生から慰謝料を受け取るまでの一般的な流れを、ステップごとに分かりやすく解説します。全体の流れを把握しておくことで、落ち着いて対応できるようになります。
事故発生から治療開始まで
事故に遭ってしまったら、パニックにならず、まずはご自身の安全を確保し、以下の初期対応を順序立てて行いましょう。この段階での対応が、後の慰謝料請求にも影響してくることがあります。
けが人がいる場合は救護が最優先ですが、その後必ず警察に連絡し事故の届け出をしましょう。どんな小さな事故でも届け出は義務であり、保険請求に必要な「交通事故証明書」を発行してもらうためにも不可欠です。
加害者の氏名、住所、電話番号、車のナンバー(車両登録番号)、加入している自賠責保険会社名、任意保険会社名、証明書番号などを正確に確認し、メモしておきましょう。可能であれば運転免許証や車検証を見せてもらうと確実です。
ご自身が加入している自動車保険会社にも、事故に遭ったことを速やかに連絡しましょう。搭乗者傷害保険や弁護士費用特約など、利用できる保険があるか確認できます。
事故直後は興奮していて痛みを感じにくくても、後から症状が出ることがよくあります。まずは必ず病院(整形外科など)で医師の診察を受け、診断書をもらいましょう。この診断書が、ケガと事故との因果関係を証明する重要な書類となります。
医師からの指示や同意が得られたら、加害者側の保険会社に接骨院へ通院したい旨を伝えましょう。これにより、後の治療費支払いがスムーズになります。
症状固定と後遺障害等級認定
治療を続けても、残念ながらケガの症状がそれ以上改善しない状態になることがあります。これを「症状固定」といい、この診断は医師が行います。
症状固定後も何らかの症状が残ってしまった場合には、「後遺障害」として等級認定の手続きを進めることになります。
医師が「これ以上治療を続けても症状の改善は見込めない」と判断した時点が症状固定日となります。いつを症状固定とするか、判断するのは保険会社ではなく医師です。
症状固定後も後遺症が残った場合、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この書類は、後遺障害等級認定を受けるために非常に重要なものです。
作成してもらった後遺障害診断書などの必要書類を揃え、加害者が加入する自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定を申請します。この手続きは、被害者自身で行う「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」の2つの方法があります。
後遺障害等級認定の制度や請求方法については、後遺障害等級への認定で補償される賠償金についてわかりやすく解説 | 日本損害保険協会でも詳しい情報が提供されていますので、参考にしてください。
保険会社との示談交渉
ケガの治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認定されるなどして損害額全体が確定すると、いよいよ加害者側の任意保険会社との間で、慰謝料を含む損害賠償金の具体的な金額についての話し合い(示談交渉)が始まります。
通常、治療期間中の損害(治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料)と、後遺障害が認定された場合は後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料、逸失利益)のすべてが明らかになった時点で、保険会社から示談案(損害賠償額の提示)が送られてきます。
保険会社から提示される慰謝料額は、多くの場合、最低ラインの補償でしかない自賠責保険基準で計算されており、弁護士が交渉する際に用いる弁護士基準(裁判基準)よりも低額であることがほとんどです。提示された内容を鵜呑みにせず、各項目が適切に評価されているか、計算に誤りがないかなどを慎重に確認しましょう。
提示額に納得がいかない場合は、その根拠を示して保険会社と交渉します。ご自身での交渉が難しいと感じたり、より適切な賠償額を求めたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼することを検討しましょう。
もし保険会社との交渉がまとまらない場合は、公益財団法人 交通事故紛争処理センターのような中立的な第三者機関に、和解のあっせんを申し立てるという方法もあります。
示談成立と慰謝料の受け取り
保険会社との示談交渉で双方が合意に達すると、示談が成立し、慰謝料を含む損害賠償金が支払われます。示談は一度成立すると原則やり直しがきかないため、内容をしっかり確認することが大切です。
合意した内容を書面にした「示談書」(保険会社によっては「免責証書」などと呼ばれることもあります)が保険会社から送られてきます。賠償金の総額、内訳、支払日、支払方法などが明記されているか、合意した内容と相違がないかを細部まで確認しましょう。不明な点があれば、署名・捺印する前に必ず確認してください。
内容に問題がなければ、示談書に署名・捺印し、保険会社に返送します。
示談書が保険会社に到着し、手続きが完了すると、通常は数日から数週間程度で、示談書に記載された指定の銀行口座に慰謝料を含む損害賠償金が振り込まれます。これで、交通事故に関する一連の慰謝料請求手続きは完了となります。
この流れはあくまで一般的なケースです。事故の状況やケガの程度によっては、手順が前後したり、追加の手続きが必要になることもあります。不安なことや分からないことがあれば、早めに専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
まとめ
交通事故で接骨院に通院した場合でも慰謝料は請求できます。
慰謝料の算定基準には自賠責保険基準、任意保険基準、そして最も正当かつ高額の弁護士基準の3つが存在します。適切な慰謝料を受け取るためには、医師の同意を得て通院する、保険会社へ事前に連絡するなど、いくつかの注意点を守ることが重要です。
もし慰謝料額や手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することで、より有利な条件での解決が期待できるでしょう。
仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください
仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。
お気軽にご相談、ご予約ください。
「整形外科との併用」「正しい通院」を徹底サポート!