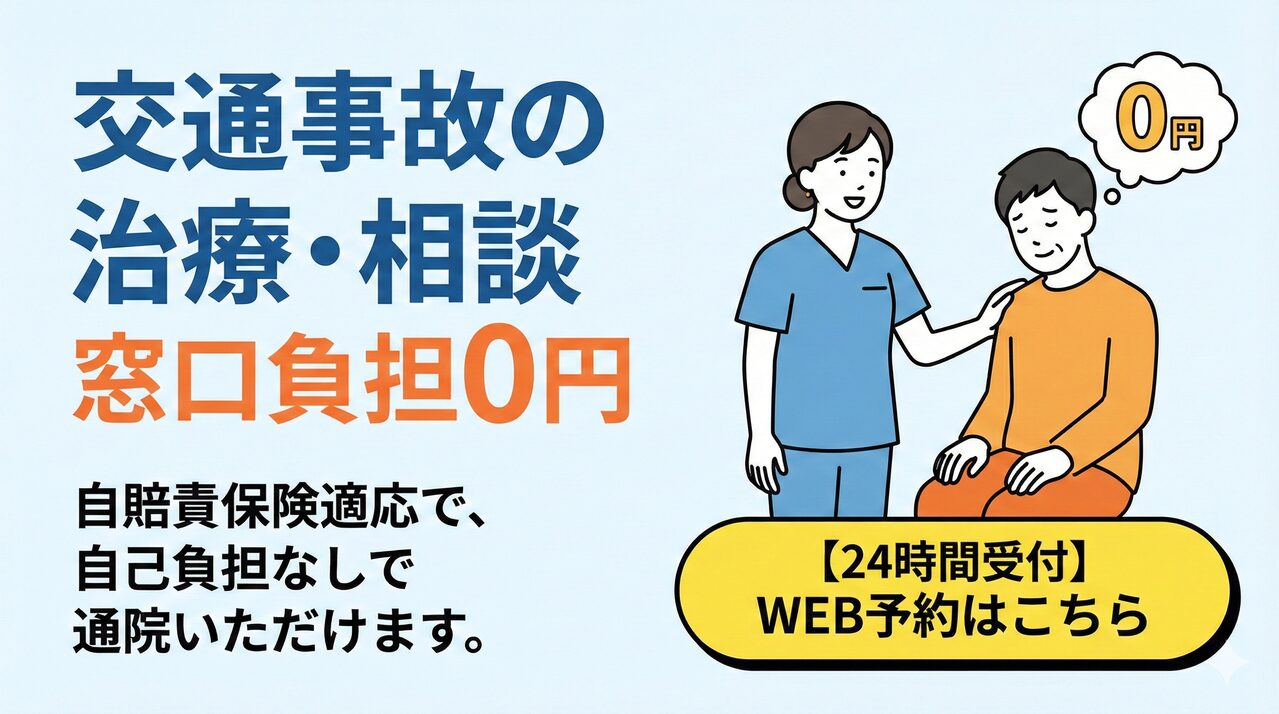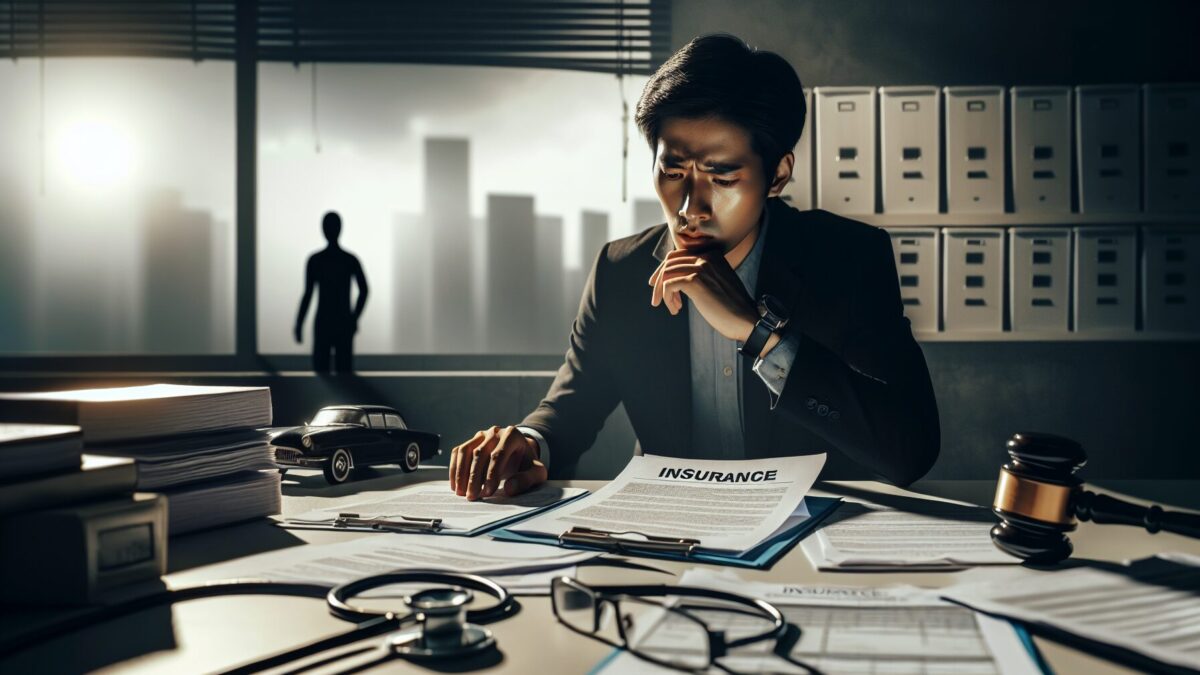交通事故に遭い治療中の方で、保険会社からの治療費打ち切りに不安を感じていませんか?
この記事では、打ち切りの定義や原因、打診された際の対処法、そして事前にできる予防策まで網羅的に解説します。
治療費打ち切りは保険会社の一方的な判断で決まるものではありません。症状固定まで適切な治療を受け、正当な賠償を得るための具体的なステップが分かります。
交通事故治療費の「打ち切り」とは何か?基本的な仕組みを理解する
交通事故に遭い、治療を受けている最中に、突然加害者側の保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。これが交通事故における「治療費打ち切り」です。
多くの場合、被害者にとっては予期せぬ通告であり、今後の治療や生活に大きな不安を感じさせる事態となります。
この章では、まず治療費打ち切りが何を意味するのか、そしてなぜ起こるのか、その基本的な仕組みについて詳しく解説します。
治療費打ち切りの定義と保険会社の意図
交通事故における治療費打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が、被害者の治療にかかる費用(医療機関への直接支払いなど)を一方的に停止することを指します。
通常、交通事故の治療費は、加害者が加入している任意保険会社が「一括対応」という形で、病院や整骨院などの医療機関に直接支払ってくれます。これにより、被害者は一時的に治療費を立て替える負担なく治療に専念できます。
しかし、治療が一定期間続くと、保険会社は「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)に至った」あるいは「治療の必要性が低い」と判断し、治療費の支払いを打ち切る打診や決定通知をしてくることがあります。
保険会社が治療費打ち切りを行う主な意図は、自社が負担する賠償金の総額を抑えることにあります。
特に治療が長引くと、治療費だけでなく入通院慰謝料や休業損害なども増額していくため、保険会社としては早期に治療を終了させたいと考えます。
また、任意保険会社は自賠責保険の傷害部分の上限である120万円を超えた部分を負担するため、支払いを120万円以内に収めようとする傾向があります。
この「一括対応」は、あくまで保険会社が任意で行っているサービスであり、法的な義務ではありません。そのため、保険会社は自社の判断基準に基づき、打ち切りを行うことができるのです。
ただし、保険会社による「打ち切り=治療の終了」ではありません。保険会社が支払いを打ち切ったとしても、医師が治療の必要性を認めている限り、被害者は治療を続ける権利があります。
打ち切り後の治療費の請求方法については、後の章で詳しく解説します。
交通事故治療費が支払われる流れ(一括対応)
交通事故による怪我の治療費は、原則として加害者が負担すべき損害賠償の一部です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や、手続きが煩雑になることを避けるため、通常は加害者が加入している保険会社が治療費の支払いを行います。
この支払いプロセスには、主に以下の2つの保険が関わってきます。
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険):法律で加入が義務付けられている強制保険です。人身事故の被害者救済を目的とし、傷害部分については治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせて最大120万円までの補償を行います。
- 任意保険:自賠責保険だけではカバーしきれない損害を補償するために、ドライバーが任意で加入する保険です。治療費が自賠責保険の上限額を超えた場合や、対物賠償、弁護士費用特約などが含まれます。
多くのケースでは、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分も含めて治療費全額を医療機関に直接支払う「一括対応(いっかつたいおう)」というサービスを行います。これにより、被害者は窓口での支払いが不要となり、治療に専念しやすくなります。
保険会社は、立て替えた治療費のうち自賠責保険から支払われるべき部分を、後日自賠責保険に請求します。
| 保険の種類 | 補償内容 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 強制加入。人身損害の基礎的な補償(傷害上限120万円)。 | 任意保険会社が一括対応の中で立て替え払いすることが多い。 |
| 任意保険 | 任意加入。自賠責保険を超える損害や、対物損害などを補償。 | 治療費、慰謝料、休業損害など、自賠責保険分を含めて一括対応を行うことが多い。 |
注意点として、加害者が任意保険に加入していない場合、治療費はまず自賠責保険の範囲内で支払われますが、上限の120万円を超えた分については、加害者本人に直接請求するか、被害者自身の健康保険や人身傷害保険などを利用して治療を続けることになります。
任意保険の内容は会社や契約によって異なるため、どのような補償が受けられるか確認したい場合は、保険比較サイトなどを参考にすると良いでしょう。
保険会社が負担する治療費の範囲と限界
加害者側の保険会社(主に任意保険会社の一括対応)が負担する治療費は、交通事故によって受けた傷害の治療に必要かつ相当な範囲に限られます。具体的には、以下のような費用が一般的に対象となります。
| 費用の種類 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 診察料・検査料 | 初診料、再診料、レントゲン、MRI、CTなどの画像検査費用 |
| 投薬料・注射料 | 処方された薬剤の費用、痛み止めの注射など |
| 処置料・手術料 | 創傷処置、ギプス固定、リハビリテーション、手術費用など |
| 入院料 | 入院基本料、個室使用料(必要性が認められる場合)など |
| 通院交通費 | 公共交通機関、タクシー(必要性が認められる場合)、自家用車のガソリン代など |
| 診断書・証明書費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 |
| 装具・器具代 | 松葉杖、コルセットなど、医師が必要と認めたもの |
ただしこれらの費用であっても、保険会社が「治療の必要性がない」「過剰な診療である」「事故との因果関係が不明確」などと判断した場合には、支払いが拒否されたり、打ち切りの対象となったりすることがあります。
例えば、医師の指示に基づかない頻繁な通院や、効果の乏しい治療の長期継続、高額すぎる個室代などは、支払いが認められない可能性があります。
また、保険会社が治療費を負担するのには「限界」があります。最も明確な限界は「症状固定」の診断です。症状固定とは、医学的にこれ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が診断された状態を指します。
原則として、症状固定日以降の治療費は、交通事故による損害とは認められず、保険会社の支払い対象外となります。保険会社が治療費の打ち切りを打診してくるのは、この症状固定の時期が近いと判断した場合が多いのです。
このように、保険会社が負担する治療費には範囲と限界があることを理解しておくことが、打ち切り問題に対応する上で重要となります。
なぜ?交通事故治療費が打ち切られる主な原因
交通事故によるケガの治療中、突然、加害者側の任意保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。被害者にとっては、まだ痛みや症状が残っているのに治療を続けられなくなるのではないかと、大きな不安を感じる瞬間です。
では、なぜこのような「治療費打ち切り」が起こるのでしょうか。その主な原因を詳しく見ていきましょう。
治療期間の長期化と「症状固定」の判断
交通事故後の治療が長引くと、保険会社は治療費の打ち切りを検討し始めます。 保険会社が重視するのが「症状固定」という概念です。
症状固定とは、「医学的に一般に認められた治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態」を指し、これ以上治療を続けても症状の大幅な改善が見込めないと判断されることを意味します。
症状固定の判断は医師のみが行える行為ですが、保険会社が過去の事例や傷病名ごとの一般的な治療期間を参考に、独自に症状固定時期を判断し打ち切りを打診してくるケースが非常に多いのが実情です。
保険会社は、無限に治療費を支払い続けるわけにはいかず、損害賠償額を確定させるためにもどこかのタイミングで治療の終了(症状固定)を促す必要があります。
特に、治療が漫然と続けられている(効果の薄い治療がだらだらと続けられている)と判断されると、打ち切りの対象となりやすくなります。
むちうち・打撲・骨折など傷病別の目安期間
保険会社が治療費打ち切りを検討する際、傷病名ごとに設けられた一般的な治療期間の目安が存在します。
有名なものでは「DMK136」があり、D(打撲)1ヶ月・M(むちうち)3ヶ月・K(骨折)6ヶ月と言われています。実際に当院でも、この期間を目安に相手方保険会社から催促のお電話を頂くことが多いです。
以下は一例ですが、あくまで目安であり、本来は個々の症状や回復状況によって必要な治療期間は異なります。
| 傷病名 | 一般的な治療期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| むちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫など) | 3ヶ月〜6ヶ月程度 | 症状の重さや神経症状の有無により変動します。 |
| 打撲 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | 部位や程度により異なります。 |
| 骨折 | 6ヶ月〜1年以上 | 骨癒合の状況やリハビリの必要性により大きく変動します。手術の有無も影響します。 |
| 神経症状(しびれ、麻痺など) | 6ヶ月以上 | 症状固定まで長期化する傾向があります。 |
これらの目安期間を超えて治療が続いている場合、保険会社から治療状況の確認や、症状固定の打診が行われる可能性が高まります。
しかし、目安期間が過ぎたからといって、必ずしも治療を終了しなければならないわけではありません。 医師が必要と判断し、症状の改善が見られる、あるいは生活に支障をきたす症状が残存している場合は、治療継続の必要性を主張することが重要です。
(参考:損害保険料率算出機構 自賠責保険基準料率 ※具体的な期間目安は明記されていませんが、保険料率算出の基礎情報として傷病に関するデータが含まれます)
医師による治療終了(症状固定)の診断
治療費打ち切りの最も正当な根拠となるのが、担当医師による「症状固定」の診断です。
医師が診察や検査の結果、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないと判断した場合、症状固定と診断します。
この医師の判断は、保険会社にとっても治療費支払いを終了する大きな理由となります。通常、保険会社は定期的に医療照会(治療状況の確認)を行い、医師から症状固定の情報を得ると、それを根拠に治療費の打ち切りを通知してきます。
しかし、被害者自身がまだ痛みや不調を感じており、治療継続を希望する場合もあります。そのような場合は、まず担当医師に、なぜ症状固定と判断したのか、具体的な理由を確認しましょう。
そして、現在の症状や治療継続の希望を明確に伝え、再度検討してもらえないか相談することが大切です。場合によっては、他の医師の意見を聞く「セカンドオピニオン」を求めることも有効な手段となります。
保険会社の判断基準:通院頻度や治療内容
医師がまだ症状固定と診断していなくても、保険会社が独自の判断で治療費の打ち切りを打診してくることがあります。その判断基準として、主に以下の点が考慮されます。
- 通院頻度: 通院頻度が著しく低い場合(例:月に数回程度)、保険会社は「症状が軽快した」「治療の必要性が低い」と判断しやすくなります。 特に、理由なく長期間通院が途絶えると、治療の意思がないと見なされ、打ち切りの強い理由となります。
- 治療内容: 検査ばかりで具体的な治療が行われていない、あるいは効果の薄い治療(湿布や痛み止めの処方のみなど)が漫然と続けられている場合、治療の必要性が低いと判断されることがあります。
- 症状の一貫性: 被害者が訴える症状と、医師の診断や検査結果に乖離がある場合、保険会社は症状の信憑性を疑い、打ち切りを検討することがあります。
- 事故態様と症状の整合性: 事故の規模(軽微な物損事故など)に対して、重すぎる症状を訴えていると判断された場合、治療の必要性が疑問視されることがあります。
- 医療照会への回答: 保険会社が医療機関に行った照会に対し、医師からの回答が「症状は改善傾向」「もうしばらく様子見」といった曖昧な内容が続くと、打ち切り判断に傾く可能性があります。
保険会社は、自賠責保険の傷害部分の上限額(120万円)を超えると、任意保険会社自身の負担が発生するため、治療費をできるだけ抑えたいという経済的な動機も背景にあります。そのため、上記の基準に照らして、治療の必要性や相当性に疑問があると判断すると、早期に打ち切りを打診してくる傾向があります。
整骨院・接骨院での治療は打ち切られやすい?
整形外科などの病院ではなく、整骨院や接骨院(柔道整復師による施術)を中心に通院している場合、比較的早期に治療費の打ち切りを打診される傾向があります。 これにはいくつかの理由があります。
- 医師の診断・指示の不在: 整骨院・接骨院での施術は、本来、医師の診断や指示に基づいて行われるべきですが、実際には医師の関与なく通院が続けられるケースも少なくありません。保険会社は、医師による医学的な管理・判断がなされていない治療について、その必要性や有効性を疑問視する傾向があります。
- 施術内容の評価: 整骨院・接骨院での施術は、マッサージや電気療法などが中心となることが多く、保険会社からは「症状改善に不可欠な医療行為」とは見なされにくい場合があります。特に、漫然と長期間同じような施術が続いていると、「慰安目的」と判断され、打ち切りの対象となりやすくなります。
- 症状固定判断の難しさ: 整骨院・接骨院では、医師のように法的な意味での「症状固定」の診断を行うことはできません。そのため、治療のゴールが見えにくく、保険会社としては早期に区切りをつけたいと考えがちです。
ただし、整骨院・接骨院での治療が全く認められないわけではありません。
医師がその必要性を認め、定期的に整形外科等での診察も受け、連携を取りながら治療を進めている場合は、保険会社も治療費の支払いを継続する可能性が高まります。
重要なのは、医師の管理下で、症状改善のために必要な施術を受けていることを明確に示すことです。
(参考:厚生労働省 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて ※労災保険に関する資料ですが、柔道整復師の施術の位置づけに関する参考情報)
これらの原因を理解しておくことは、不当な治療費打ち切りを防ぎ、必要な治療を継続するために非常に重要です。次の章では、実際に打ち切りの連絡を受けた場合に取るべき行動について解説します。
保険会社から治療費打ち切りの連絡が!まず取るべき行動
交通事故による怪我の治療中に、加害者側の任意保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」という連絡(打診や通知)を受けることがあります。まだ痛みや症状が残っている場合、このような連絡は被害者にとって大きな不安やストレスの原因となります。
しかし、慌てて保険会社の言い分に同意してしまうのは禁物です。まずは冷静に状況を把握し、適切な対応を取ることが、ご自身の権利を守り、必要な治療を継続するために非常に重要です。
この章では、保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた際に、まず何をすべきか、どのような点に注意すべきか、そして治療継続の必要性をどのように主張すればよいかについて、具体的なステップを解説します。
打ち切りの打診・通知を受けたら最初に確認すること
保険会社の担当者から治療費打ち切りの連絡(電話または書面)を受けたら、感情的にならず、まずは以下の点を落ち着いて確認し、記録に残しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容・ポイント |
|---|---|
| 連絡の形式 | 電話での連絡か、書面での通知かを確認します。電話の場合は、後日必ず書面での通知(理由や日付が明記されたもの)を送ってもらうよう依頼しましょう。 |
| 連絡してきた担当者 | 保険会社の名称、担当者の氏名、所属部署、連絡先を正確に記録します。 |
| 打ち切りの理由 | なぜ治療費の支払いを打ち切るのか、具体的な理由を明確に確認します。「治療期間が長いから」「症状固定と判断したから」「通院頻度が低いから」など、理由によって対応方法が変わってきます。曖昧な説明の場合は、根拠を詳しく尋ねましょう。 |
| 打ち切りの時期 | いつから治療費の支払いが停止されるのか、具体的な日付を確認します。 |
| 医師の意見の反映 | 保険会社の判断が、主治医の意見(症状固定の診断など)に基づいているのかを確認します。もし、まだ医師から症状固定の診断を受けていない場合は、その旨を伝えましょう。 |
| 今後の手続き | 打ち切り後の手続きや、異議申し立ての方法などについて説明があれば、内容を正確に把握します。 |
これらの情報を正確に記録しておくことは、後の交渉や専門家への相談時に非常に役立ちます。電話でのやり取りも、日時、担当者名、会話内容をメモに残す習慣をつけましょう。
同意してはいけないケースとは?
保険会社は、様々な理由をつけて治療費の打ち切りを打診してきますが、まだ治療が必要だと感じているにも関わらず、安易に同意書などにサインをしてはいけません。
一度同意してしまうと、後から治療の必要性を主張するのが困難になる可能性があります。特に、以下のようなケースでは、絶対に同意すべきではありません。
- 痛みや痺れなどの自覚症状が残っており、日常生活に支障が出ている場合
- 主治医が「まだ治療継続が必要」「症状固定には至っていない」と判断している場合
- 保険会社が提示する打ち切りの理由に納得できない、または根拠が不明確な場合
- 医師による正式な症状固定の診断を受けていない場合
- 保険会社の担当者から、十分な説明がないまま一方的に同意を迫られている場合
- 「同意しないと今後の示談交渉で不利になる」といった、プレッシャーを感じさせるような説明を受けた場合
保険会社は営利企業であり、支出を抑えたいという意図があることを念頭に置く必要があります。
被害者自身の体の状態と、医師の専門的な意見を最も重視し、納得できない要求には毅然とした態度で臨むことが大切です。
治療継続の必要性を主張する方法
相手方保険会社に治療費打ち切りの判断を覆してもらい、治療費の支払いを継続してもらうためには、「治療の必要性」と「治療の有効性」を客観的な証拠に基づいて具体的に主張する必要があります。
以下のステップで対応を進めましょう。
まず、相手方保険会社から治療費打ち切りの連絡があったことを主治医に伝え、現在の症状(痛みの部位、程度、頻度、日常生活への影響など)を具体的かつ正確に説明します。その上で、今後の治療方針や、治療継続の必要性について医師の意見を確認しましょう。医師が治療継続の必要性を認めている場合は、その旨を診断書や意見書に記載してもらうよう依頼します。この医師の意見は、保険会社との交渉において最も強力な根拠の一つとなります。
医師の診断書や意見書に加えて、治療の必要性を裏付ける客観的な証拠を収集・整理します。
・最新の診断書・意見書: 症状の詳細、今後の治療計画、治療継続の必要性が明記されたもの。
・検査結果: MRI、CT、レントゲンなどの画像検査結果や、神経学的検査の結果など、症状の原因や状態を示す客観的なデータ。
・診療報酬明細書(レセプト): これまでの治療内容や頻度を示す記録。
・看護記録やリハビリテーション記録: 入院中の記録やリハビリの経過を示す記録。
・症状のメモ・日記: 日々の痛みの変化、どのような時に症状が悪化するか、日常生活で困っていることなどを具体的に記録したもの。これは自覚症状を伝える上で重要な資料となります。
収集した証拠(特に医師の診断書・意見書)をもとに、保険会社に対して治療継続の必要性を具体的に主張します。電話での口頭説明だけでなく、治療継続を求める理由と根拠を記載した書面(可能であれば内容証明郵便などを利用)で申し入れることが望ましいです。書面でやり取りすることで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、こちらの主張を明確に記録として残すことができます。 交渉の際は、感情的にならず、冷静かつ論理的に説明することを心がけましょう。
保険会社との交渉が難航する場合や、保険会社の対応に納得がいかない場合は、早期に交通事故問題に詳しい弁護士に相談することを強く推奨します。
- 保険会社との交渉を代行してもらえるため、精神的な負担が軽減される。
- 法的な観点から、治療継続の必要性を的確に主張してもらえる。
- 保険会社に対して対等な立場で交渉を進めることができる。
- 適切な後遺障害等級認定や、最終的な示談交渉までサポートを受けられる。
ご自身やご家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用を保険で賄える場合がありますので、確認してみましょう。 また、弁護士への相談以外にも、以下のような中立的な第三者機関を利用することも可能です。
- 日弁連交通事故相談センター: 弁護士による無料相談や示談あっ旋を行っています。
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター: 損害賠償に関する紛争解決をサポートしています。
治療費打ち切りの連絡を受けても、すぐに諦める必要はありません。適切な手順を踏み、必要であれば専門家の力も借りながら、粘り強く対応していくことが重要です。
交通事故治療費の打ち切りを防ぐための予防策
交通事故に遭われた際、治療に専念したいにもかかわらず、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースは少なくありません。しかし、適切な予防策を講じることで、不当な打ち切りリスクを大幅に減らすことが可能です。
ここでは、治療費打ち切りを防ぐために実践すべき具体的な方法を解説します。
医師との連携:症状を正確に伝え、定期的にカルテに記載して頂く
保険会社が治療費支払いの継続・打ち切りを判断する上で、最も重視するのが医師の診断と所見です。そのため、担当医師との良好な連携体制を築くことが、打ち切りを防ぐための最重要ポイントとなります。
まず、診察時にはご自身の症状を具体的かつ正確に伝えることを心がけましょう。
「痛い」「だるい」といった抽象的な表現だけでなく、「いつ、どこが、どのように痛むのか」「どのような動作で痛みが増すのか」「日常生活のどの場面で支障が出ているのか」などを詳細に説明することが重要です。これにより、医師は症状の深刻度や治療の必要性を正確に把握しやすくなります。
そして、伝えた症状や治療経過、今後の治療方針などを、必ずカルテ(診療録)に詳細に記載してもらうようお願いしましょう。
カルテは、治療の必要性や相当性を証明する客観的な証拠となります。口頭で伝えただけでは、後々「言った・言わない」の水掛け論になりかねません。定期的な診察を通じて、症状の変化や治療効果を継続的に記録してもらうことが、保険会社への有力な対抗材料となります。
また、保険会社から治療状況について照会があった際に、医師が的確に回答できるよう、日頃からコミュニケーションを密にしておくことも大切です。
必要であれば、定期的に診断書や経過報告書を作成してもらい、保険会社に提出することも有効な手段です。医師との信頼関係に基づいた連携が、治療費打ち切りを防ぐための基盤となります。
参考情報として、医師とのコミュニケーション方法については、日本医師会のウェブサイトで患者と医師のより良い関係構築のための情報が提供されています。
治療の必要性を示す記録と証拠の集め方
医師の診断に加え、治療の必要性や継続性を客観的に示すための記録や証拠を、被害者自身が意識的に収集・保管しておくことも、打ち切りを防ぐ上で非常に重要です。
これらの資料は、保険会社との交渉や、万が一紛争になった場合に、ご自身の主張を裏付ける強力な武器となります。
具体的にどのような記録・証拠を集めるべきか、その重要性とともに以下に解説します。
通院記録、領収書、日々の症状メモの重要性
治療の必要性を立証するためには、以下のような記録を整理・保管しておくことが推奨されます。
| 記録・証拠の種類 | 具体的な内容 | 重要性・役割 |
|---|---|---|
| 通院記録 | 通院した日付、医療機関名、診療科、担当医名、簡単な治療内容などを記録したもの。 | 継続的かつ定期的に治療を受けていることを示す基本的な証拠です。通院頻度が低い、または不規則だと、保険会社に「治療の必要性が低いのでは?」と疑われる可能性があります。 |
| 診断書・診療報酬明細書(レセプト) | 医師が作成する傷病名、症状、治療内容、今後の見通しなどが記載された書類。レセプトは医療機関から保険会社へ提出される治療費の明細書です。 | 医学的な見地から治療の必要性や症状の存在を証明する最も重要な証拠です。定期的に取得・確認し、内容に齟齬がないかチェックしましょう。レセプトの開示請求も可能です。 |
| 検査結果・画像資料 | レントゲン、MRI、CTなどの画像検査の結果や、その他の検査データ。 | 症状の原因や程度を客観的に示す証拠となります。特に、むちうちなど他覚的所見が得られにくい症状の場合、画像所見は重要度を増します。 |
| 領収書・明細書 | 診察料、薬剤費、交通費(通院にかかった費用)などの領収書や明細書。 | 実際に治療費や関連費用が発生していることを証明する証拠です。後々の損害賠償請求のためにも、必ず保管しておきましょう。 |
| 日々の症状メモ(日記) | 痛みやしびれの部位・程度、症状が現れる状況、日常生活への支障、服用した薬、医師からの指示などを具体的に記録したもの。 | 自覚症状の推移や治療による変化を示す重要な補足資料です。特に、むちうちのように他覚的所見が得にくい場合、症状の一貫性を主張する上で役立ちます。スマートフォンアプリなどを活用するのも良いでしょう。 |
これらの記録は、単に保管するだけでなく、整理しておくことが大切です。時系列に沿ってファイリングするなど、いつでも参照・提出できる状態にしておきましょう。
証拠の収集・管理方法について不明な点があれば、交通事故に詳しい弁護士に相談するのも有効です。例えば、交通事故紛争処理センターなどの機関も参考になります。
保険会社との適切なコミュニケーション方法
加害者側の保険会社担当者とのコミュニケーションも、治療費打ち切りを回避するための重要な要素です。担当者との関係を良好に保ち、治療状況を適切に伝えることで、一方的な打ち切りを防ぎやすくなります。
ただし、相手はあくまで加害者側の立場であり、支払う保険金を抑えたいという意図を持っていることを忘れてはいけません。不用意な発言は避け、冷静かつ丁寧な対応を心がける必要があります。
具体的には、以下の点に注意してコミュニケーションを取りましょう。
| コミュニケーションのポイント | 具体的な対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 定期的な状況報告 | 担当者から連絡があった場合は誠実に対応し、現在の症状や治療状況、医師からの指示などを簡潔に伝える。必要であれば、診断書や経過報告書を提出する。 | 過度に詳細な個人情報や、治療に関係のない話は避ける。症状について「もう大丈夫」「だいぶ良くなった」など、安易な改善報告は、打ち切りの口実を与えかねないため慎重に。 |
| 冷静かつ丁寧な態度 | 感情的にならず、冷静な口調で話す。担当者の説明や質問には、可能な範囲で協力的な姿勢を示す。 | 担当者の言うことを鵜呑みにせず、疑問点は必ず確認する。同意を求められても、安易に承諾しない(特に症状固定や治療終了に関する同意)。 |
| 記録の保持 | 担当者との電話内容(日時、担当者名、話した内容)をメモに残す。重要なやり取りは書面(メールなど)で行うか、書面での確認を求める。 | 言った・言わないのトラブルを防ぐため、記録は必ず残す。録音も有効な手段ですが、相手に断りを入れるのが望ましいでしょう。 |
| 治療継続の意思表示 | 医師が治療継続の必要があると判断している場合は、その旨を明確に伝える。「まだ痛みがあり、医師からも治療を続けるよう言われています」など。 | 自身の判断だけでなく、必ず医師の診断に基づいていることを強調する。 |
保険会社とのやり取りに不安を感じる場合や、担当者から高圧的な態度を取られるような場合は、無理に対応せず、弁護士に相談することを検討しましょう。
弁護士が間に入ることで、対等な立場で交渉を進めることが可能になります。自賠責保険に関する情報は、損害保険料率算出機構の自賠責保険ポータルサイトなども参考になります。
計画的な通院と無理のないリハビリ計画
治療の必要性を保険会社に納得してもらうためには、計画的かつ継続的な通院が不可欠です。
自己判断で通院を中断したり、通院間隔が不規則になったりすると、「もう治ったのではないか」「治療の必要性が低いのではないか」と判断され、打ち切りの格好の理由を与えてしまいます。
医師と相談の上、適切な通院頻度を守り、治療計画に沿ってコンスタントに通院を続けましょう。仕事や家庭の事情でどうしても通院できない日がある場合は、事前に医師や保険会社に相談しておくことが望ましいです。無断での中断は避けなければなりません。
また、リハビリテーションについても、医師の指示に基づき、無理のない範囲で計画的に進めることが重要です。
早期回復を目指すあまり、過度なリハビリを行ったり、効果の疑わしい施術を受けたりすることは、かえって症状を悪化させたり、保険会社から治療の妥当性を疑われたりする原因にもなりかねません。
リハビリの内容や頻度、効果についても、定期的に医師の診察を受け、その評価をカルテに記載してもらうようにしましょう。リハビリの進捗状況や、それによって症状がどのように変化しているかを客観的に記録しておくことが、治療継続の必要性を裏付ける上で役立ちます。
交通事故後のリハビリテーションに関する一般的な情報は、日本リハビリテーション医学会などのウェブサイトでも確認できます。
これらの予防策を講じることで、交通事故治療費の不当な打ち切りリスクを低減し、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。
治療費打ち切りに納得できない場合の対処法
保険会社から一方的に治療費の打ち切りを宣告されたとしても、諦める必要はありません。治療の必要性が医学的に認められる限り、治療費の支払いを求める権利があります。
ここでは、打ち切りに納得できない場合に取るべき具体的な対処法を解説します。
保険会社への異議申し立て・交渉の進め方
まず、保険会社に対して治療費打ち切りの判断に異議を申し立て、交渉を行うことが第一歩となります。感情的にならず、冷静かつ論理的に対応することが重要です。
具体的な進め方は以下の通りです。
まず、保険会社の担当者に連絡を取り、治療費を打ち切る具体的な理由を書面で提示してもらうよう求めましょう。理由が曖昧な場合は、詳細な説明を要求します。
主治医に保険会社から打ち切りの連絡があったことを伝え、現在の症状や今後の治療の必要性について相談します。治療継続が必要であるとの医学的見解が得られれば、診断書や意見書を作成してもらいましょう。この意見書が交渉の強力な根拠となります。
医師の意見書などを添えて、保険会社に対して書面(内容証明郵便などが望ましい)で異議を申し立てます。「治療継続の必要性があること」「打ち切りは不当であること」を明確に主張しましょう。電話での交渉も可能ですが、後々の証拠として残すためにも書面でのやり取りが推奨されます。
- 医学的根拠を示す
医師の診断書や意見書に基づき、治療が必要な具体的な症状や、治療による改善の見込みを説明します。 - 症状の一貫性を伝える
事故当初からの症状の経過や、日常生活への支障などを具体的に伝え、治療が必要であることを訴えます。日々の症状メモなども役立ちます。 - 冷静な態度を保つ
感情的にならず、客観的な事実に基づいて冷静に交渉を進めることが重要です。
ただし、被害者自身での交渉は、保険会社の担当者との知識や経験の差から、必ずしも有利に進むとは限りません。
交渉が難航する場合や、保険会社の対応に納得できない場合は、次のステップとして弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に相談するメリットとタイミング
保険会社との交渉がうまくいかない場合や、法的な観点から適切な対応を取りたい場合には、交通事故問題に精通した弁護士に相談することが有効な手段です。
弁護士に相談・依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 法的な専門知識に基づく交渉: 弁護士は法律と過去の判例に基づいて、保険会社と対等に交渉を進めることができます。治療継続の必要性を法的に主張し、不当な打ち切りに対抗します。
- 保険会社への対応代行: 保険会社との連絡や交渉をすべて弁護士に任せることができるため、被害者自身の精神的・時間的な負担が大幅に軽減されます。治療に専念できる環境が整います。
- 適切な賠償額の獲得: 治療費だけでなく、慰謝料や休業損害など、他の損害賠償項目についても、裁判基準(弁護士基準)での請求を目指すため、最終的に受け取れる賠償額が増額する可能性があります。
- 後遺障害等級認定のサポート: 症状固定後、後遺障害が残った場合には、適切な後遺障害等級認定を受けられるよう、申請手続きのサポートも期待できます。
弁護士に相談するタイミングとしては、以下のような時点が考えられます。
- 保険会社から治療費打ち切りの打診・通知があった時点
- 保険会社との交渉が平行線で進展しない時点
- 症状固定の時期や後遺障害について不安がある時点
- 提示された示談金額に納得できない時点
できるだけ早い段階で相談することで、より有利な状況で交渉を進められる可能性が高まります。多くの法律事務所では初回無料相談を実施していますので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
交通事故に強い弁護士を探すには、日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトなどを活用できます。
弁護士費用特約の活用
弁護士への依頼を検討する際に気になるのが費用ですが、「弁護士費用特約」が付帯されていれば、費用負担を気にせずに弁護士に依頼できる可能性があります。
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯されている特約の一つで、弁護士に相談・依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金など)を自分の保険会社が負担してくれる制度です。
多くの場合、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までといった上限が設けられていますが、交通事故の示談交渉や訴訟であれば、この範囲内で収まるケースがほとんどです。
嬉しいことに、この特約を利用しても翌年以降の保険料が上がったり、等級が下がったりすることはありません。
ご自身やご家族が加入している自動車保険などの契約内容を確認し、弁護士費用特約が付帯されているかチェックしてみましょう。特約が付いていれば、費用面の心配なく専門家である弁護士のサポートを受けることができます。
交通事故紛争処理センター等の第三者機関の利用
弁護士への依頼以外にも、交通事故紛争処理センター等の中立・公正な立場の第三者機関を利用して、治療費打ち切りに関する紛争解決を図る方法があります。
第三者機関は、費用を抑えつつ、専門的な知見に基づいた解決を目指したい場合に有効な選択肢となります。ただし、機関によって手続きや解決までにかかる時間が異なるため、ご自身の状況に合わせて最適な機関を選ぶことが重要です。
また、これらの機関を利用する場合でも、事前に弁護士に相談しておくことで、より有利に手続きを進められる可能性があります。
治療費の打ち切りは、被害者にとって非常に深刻な問題ですが、適切な対処法を知り、行動することで、治療継続の道を切り開くことができます。諦めずに、ご自身の権利を守るために動き出しましょう。
治療費打ち切り後の治療継続と費用負担について
相手方保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られても、医師が治療の必要性を認めている限り、治療を諦める必要はありません。しかし、治療を継続するためには、治療費をどのように負担するかが大きな問題となります。
ここでは、治療費打ち切り後に治療を続けるための具体的な方法と、その費用負担について詳しく解説します。
健康保険を使った治療への切り替え
保険会社による治療費の一括対応が打ち切られた後、まず検討すべき最も一般的な方法は、ご自身の健康保険を利用して治療を継続することです。交通事故による怪我の治療であっても、健康保険の利用は原則として可能です。
通常、交通事故治療では、加害者側の保険会社が医療機関に直接治療費を支払う「自由診療」扱いとなることが多いですが、打ち切り後は健康保険診療に切り替えることで、窓口での自己負担額を原則3割(年齢や所得により1割または2割)に抑えることができます。
健康保険を利用するためには、以下の手続きが必要です。
現在通院している病院やクリニックに、健康保険を使った治療に切り替えたい旨を伝えます。医療機関によっては、交通事故での健康保険利用に慣れていない場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは、治療費を一時的に健康保険が立て替えた後、後日、健康保険組合等が加害者(または保険会社)に対してその費用を請求するために必要な手続きです。書式や手続きの詳細は、加入している健康保険の窓口やウェブサイトで確認しましょう。
健康保険を利用するメリットは、当面の自己負担を大幅に軽減できる点にあります。ただし、注意点もあります。
- 自由診療との併用不可
健康保険診療と自由診療を同じ傷病で併用すること(混合診療)は原則として認められていません。 - 立て替え分の請求
健康保険で支払った自己負担分(3割など)や、健康保険が立て替えた分(7割など)は、最終的に加害者側に請求することになります。示談交渉や訴訟を通じて回収を目指します。 - 高額療養費制度の活用
ひと月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」を利用できます。これにより、高額な治療が必要になった場合の負担をさらに軽減できます。詳細は、厚生労働省の高額療養費制度のページをご確認ください。
治療の必要性を医師が認めているにも関わらず、保険会社が打ち切りを通告してきた場合は、まず健康保険への切り替えを検討し、治療を継続することが重要です。
労災保険が使えるケース
交通事故が「通勤中」または「業務中」に発生した場合(通勤災害・業務災害)は、健康保険ではなく労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。実は労災保険と自賠責保険は同時利用も可能なので、慰謝料の額も増額できます。
労災保険が適用される場合、治療費の自己負担は原則としてありません。
療養(補償)給付として、治療費、薬剤費、入院費などが全額支給されます。これは、保険会社から治療費が打ち切られた後でも同様です。
労災保険を利用する主なメリットは以下の通りです。
- 自己負担がない
治療費や薬剤費などの窓口負担が原則発生しません。 - 休業(補償)給付
仕事を休んだ場合の補償(給付基礎日額の80%相当)が、自賠責保険の休業損害(原則日額6,100円)よりも手厚い場合があります。 - 治療の打ち切りリスクが低い
労災保険は労働者の保護を目的としているため、症状が続く限り、比較的長期間にわたり治療給付が認められやすい傾向があります。 - 健康保険より優先適用
通勤災害・業務災害の場合は、健康保険ではなく労災保険が優先して適用されます。
労災保険を利用するには、勤務先の会社を通じて、またはご自身で所轄の労働基準監督署に必要な書類(療養補償給付たる療養の給付請求書など)を提出する必要があります。事故状況を正確に報告し、手続きを進めましょう。
ただし、労災保険と健康保険を同時に利用することはできません。また、事故が通勤災害や業務災害に該当するかどうかは、労働基準監督署が判断します。
不明な点があれば、勤務先の人事・労務担当者や労働基準監督署に相談することをおすすめします。労災保険に関する詳しい情報は、厚生労働省の労災保険に関するページで確認できます。
自費で立て替えた治療費を後から請求する方法
健康保険や労災保険を利用せずに、一旦ご自身で治療費の全額を立て替えて(自費診療)、後日その費用を加害者側の保険会社や加害者本人に請求するという方法もあります。
この方法を選択する場合、治療費が高額になる可能性があるため、一時的な経済的負担は大きくなります。しかし、治療方法の選択肢が広がる場合がある(混合診療を気にせず自由診療を受けられるなど)という側面もあります。
自費で立て替えた治療費を後から請求する流れは、主に以下のようになります。
医療機関で治療を受け、その都度、治療費の全額(10割)を自己負担で支払います。
支払った治療費の領収書、診療報酬明細書(レセプト)、診断書、医師の意見書など、治療の必要性や内容、金額を証明する書類をすべて確実に保管しておきます。これが後の請求の際に極めて重要な証拠となります。
症状固定後、または適切なタイミングで、加害者側の保険会社との示談交渉を開始します。その中で、立て替えた治療費全額(必要かつ相当な範囲)を含む損害賠償を請求します。交渉がまとまらない場合は、裁判所での訴訟を検討することになります。
この方法の最大の注意点は、立て替えた治療費が全額回収できるとは限らないことです。
保険会社は、治療の必要性や相当性について争ってくる可能性があります。特に、打ち切り後の治療期間が長引いた場合や、高額な治療、代替医療などについては、その必要性を厳しく問われる傾向にあります。
また、ご自身が加入している自動車保険に人身傷害補償保険が付帯されている場合は、そちらを利用して治療費の支払いを受けることも可能です。
人身傷害補償保険は、過失割合に関係なく保険会社の基準に基づいて損害額(治療費を含む)が支払われるため、立て替えの負担を軽減できます。保険診療での治療をお願いされることが多くなりますが、利用を検討する場合は、ご自身の保険会社に相談してみましょう。
示談交渉で治療費相当額を請求する
治療費が打ち切られた後、健康保険や自費で治療を継続した場合、その費用は最終的に加害者側に対して損害賠償として請求することになります。
この請求は、通常、すべての損害額(治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害に関する損害など)をまとめて行う「示談交渉」の中で行われます。
示談交渉において、打ち切り後の治療費を適切に請求するためには、以下の点が重要になります。
- 治療の必要性・相当性の立証
- 将来の治療費
- 弁護士への相談
以下で詳しく解説します。
治療の必要性・相当性の立証
保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、なぜ治療を継続する必要があったのか、その治療内容や期間、費用が妥当であったのかを具体的に主張し、立証する必要があります。
医師の診断書や意見書、カルテの記録などが重要な証拠となります。「まだ痛みが続いていた」「医師が治療継続を指示していた」といった事実を客観的な証拠で裏付けることが求められます。
将来の治療費
症状固定後も、リハビリや定期的な診察が必要となる場合があります。将来的に発生が見込まれる治療費についても、医師の意見を踏まえて算定し、示談交渉の中で請求することができます。
弁護士への相談
治療費打ち切り後の示談交渉は、医学的な知識や法的な主張が複雑に絡み合うため、専門家である弁護士に依頼することを強く推奨します。
弁護士は、治療の必要性を法的に構成し、適切な証拠を収集・提出することで、保険会社との交渉を有利に進めることができます。特に、後遺障害が残る可能性がある場合や、保険会社の提示額に納得できない場合は、早めに相談しましょう。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用負担を抑えて依頼できます。
示談は一度成立すると、原則として後から追加で請求することはできません。そのため、打ち切り後の治療費を含め、すべての損害項目について十分に検討し、納得できる条件で合意することが非常に重要です。
安易に示談に応じず、必要であれば専門家の助けを借りて、正当な賠償を受けられるように努めましょう。
交通事故治療費打ち切りに関するQ&A
交通事故の治療費打ち切りに関して、多くの方が抱える疑問について、Q&A形式で詳しく解説します。
打ち切り後も通院を続けたら慰謝料は減る?
保険会社から治療費の打ち切りを告げられた後も、ご自身の判断で通院を継続した場合、その期間に対する入通院慰謝料が必ずしも支払われるとは限りません。慰謝料算定の基礎となる治療期間は、原則として「症状固定日」までとされるためです。
保険会社が治療費を打ち切るのは、多くの場合「これ以上の治療による改善は見込めない(症状固定)」と判断したためです。この保険会社の判断が妥当であれば、打ち切り後の治療は「症状改善に必要不可欠な治療」とは見なされにくく、その期間の治療費はもちろん、慰謝料も損害賠償の対象外となる可能性が高いです。
ただし、医師が医学的観点から「まだ治療が必要である」と判断しており、症状固定の診断を下していない場合は状況が異なります。
この場合、保険会社の打ち切り判断が不当である可能性があります。もし、後の示談交渉や裁判などで、医師の判断通り治療の必要性が認められれば、打ち切り後、実際に症状固定と診断された日までの治療費や入通院慰謝料が認められることもあります。
重要なのは、自己判断で通院を続けることではなく、医師と緊密に連携し、治療継続の必要性を客観的な証拠(診断書やカルテ)として残しておくことです。
打ち切り後も治療が必要だと考える場合は、安易に通院をやめず、まずは弁護士に相談し、治療継続の必要性を保険会社に主張する方法を検討しましょう。
物件事故(物損事故)でも治療費は打ち切られる?
「物件事故(物損事故)」として処理されている場合であっても、原則として人身への損害(ケガ)に対する治療費は相手方の自賠責保険や任意保険から支払われます。
物件事故か人身事故かは、あくまで警察行政上の必要性から行われているだけであり、損害賠償に直接は影響しません。
人身事故にすることで、加害者側に違反点数や罰金などの行政罰が発生します。そのため、加害者側に対してムカついている場合など不満があれば、人身事故にして相手側にペナルティーを与える事ができます。
打ち切りを宣告されやすい時期は?
保険会社が治療費の打ち切りを打診・宣告してくる時期には、ある程度の傾向が見られます。必ずしも以下の時期に打ち切られるわけではありませんが、注意が必要なタイミングと言えるでしょう。
| 打ち切りが検討されやすいタイミング | 理由・背景 |
|---|---|
| 傷病別の一般的な治療期間の目安を経過した頃 | 打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月といった目安期間を過ぎると、保険会社は「そろそろ治癒または症状固定ではないか」と考えやすくなります。ただし、これはあくまで目安であり、実際の症状や回復状況は個人差が大きいです。 |
| 事故発生から一定期間(例:6ヶ月)経過後 | 特に明確な理由がなくとも、事故から半年など、ある程度期間が経過したことを区切りとして、画一的に打ち切りを打診してくるケースがあります。 |
| 通院頻度が低下してきた頃 | 月1〜2回程度の通院になったり、通院間隔が不規則になったりすると、保険会社は「症状が軽快した」「治療の必要性が低下した」と判断し、打ち切りを検討しやすくなります。 |
| 自賠責保険の傷害部分の上限額(120万円)に近づいた頃 | 治療費、休業損害、慰謝料などの合計額が自賠責保険の上限である120万円を超えると、以降は任意保険会社の負担となります。そのため、任意保険会社が自社の支出を抑える目的で、打ち切りを早めようとすることがあります。 |
これらの時期が近づいてきたら、特に意識して医師との連携を密にし、現在の症状や治療継続の必要性について、カルテへの正確な記載や診断書の作成を依頼することが、打ち切りを防ぐ上で重要になります。
症状固定と治療費打ち切りは同じ意味ですか?
「症状固定」と「治療費打ち切り」は、同じ意味ではありませんが、非常に密接に関連しています。
- 症状固定:医学的な判断です。最終的な判断は医師が行います。
「これ以上治療を続けても、その症状の回復・改善が期待できなくなった状態」を指します。症状固定の診断がなされると、その日をもって治療期間が終了し、後遺障害が残っている場合は後遺障害等級認定の申請手続きに進むことになります。また、症状固定日までの治療費、休業損害、入通院慰謝料などが損害賠償額として算定されます。 - 治療費打ち切り:保険会社(主に対応している任意保険会社)の対応・判断です。
「これ以上、当社(保険会社)としては治療費の支払いをしません」という通知や決定を指します。多くの場合、保険会社が「被害者は症状固定に至った」と判断したタイミングで行われますが、必ずしも医師の医学的な症状固定の判断と一致するとは限りません。
問題となるのは、医師がまだ治療の必要性を認めているにも関わらず、保険会社が一方的に「症状固定である」と判断し、治療費の支払いを打ち切ろうとするケースです。
保険会社の打ち切りは、あくまで保険会社の都合や内部基準による判断であり、法的に症状固定が確定したわけではありません。したがって、保険会社から打ち切りの打診があっても、医師が治療の必要性を認めている限り、安易に同意すべきではありません。
打ち切り後に後遺障害認定は受けられますか?
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後であっても、後遺障害等級認定の申請を行うことは可能です。
後遺障害等級認定の申請は、「症状固定」の診断を受けた後に行う手続きです。保険会社による治療費の打ち切りは、前述の通り、必ずしも医学的に、あるいは法的に有効な症状固定の判断とは限りません。
したがって、保険会社に治療費を打ち切られたとしても、担当医師が「症状固定」と診断すれば、その後遺症状について「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行うことができます。
ただし、注意点があります。治療費を打ち切られたことを理由に必要な治療まで中断してしまうと、症状の経過が不明瞭になったり、最終的な症状固定の判断が難しくなったりする可能性があります。
また、後遺障害診断書を作成する上で、治療経過の記録は非常に重要です。そのため、医師が必要と判断する治療は、健康保険や労災保険、自費などを利用してでも継続し、適切な時期に症状固定の診断を受けることが望ましい場合があります。
後遺障害認定の実務では、最低6ヶ月~1年間の治療期間が必要とされています。その意味でも、症状が残っているのに通院を辞めることはオススメできません。
整骨院・接骨院での治療は打ち切られやすいというのは本当ですか?
「接骨院での施術費用は病院(整形外科など)での治療費に比べて、保険会社から打ち切られやすい」というのは、残念ながら事実として聞かれることがあります。
その主な理由は以下の通りです。
- 医師の指示の重要性
- 診断行為ができない
- 施術内容への疑義
- 慰謝料が病院より高額になりやすい
詳しく解説します。
医師の指示の重要性
保険会社(特に任意保険会社)は、損害賠償の対象となる治療費について、医師による診断と指示に基づいた医療行為であることを重視します。
接骨院での施術は、医師の明確な指示がない場合、「医学的に必要な治療」ではなく「コンディショニングやリラクゼーション目的」と見なされ、治療費の支払いを拒否されたり、早期に打ち切られたりするリスクがあります。
診断行為の不可
柔道整復師は医師ではないため、診断行為(症状の原因を特定し、病名を判断すること)や症状固定の判断を行うことができません。
治療方針の決定や症状固定の判断は、必ず医師が行う必要があり、保険会社も医師の判断を基本とします。
施術内容への疑義
長期間にわたる漫然としたマッサージや電気療法などが続くと、保険会社から「症状改善に寄与していない」「過剰な施術ではないか」と疑われ、打ち切りの口実を与えてしまうことがあります。
ただし、全ての整骨院・接骨院での施術が否定されるわけではありません。骨折や脱臼、捻挫、打撲などに対する柔道整復師による施術の必要性が認められ、かつ医師がその施術の有効性を認め、(骨折や脱臼の場合は)同意・指示している場合や、保険会社が事前に通院を了承している場合は、施術費用が支払われます。
慰謝料が病院より高額になりやすい
自賠責保険において、入通院慰謝料は通院日数または治療期間をベースに決定します。治療方法が施術に限られる接骨院では、治療方法の違いから整形外科に比較して通院日数がどうしても増えてしまいます。
被害者様にとってはメリットがあるわけですが、自賠責保険の枠内で損害額を抑えたい相手側保険会社にとってはデメリットでしかありません。
整骨院・接骨院への通院で打ち切りリスクを減らすためには、以下の3点を心がけることが重要です。
- 必ず整形外科の医師の診察を定期的に並行して受ける(最低28日に1回)
- 骨折や脱臼で接骨院に通いたい場合は、事前に医師に相談し、その必要性や有効性について意見をもらい、指示や同意を得ること。むち打ちなどの捻挫、打撲、挫傷では、同意は必須ではないがある方が望ましい
- 相手方保険会社の担当者に接骨院に通院する旨を伝え、了承を得ておく
まとめ
交通事故の治療費打ち切りは相手方保険会社の一方的な判断で行われることがありますが、必ずしも受け入れる必要はありません。
治療の長期化や症状固定が主な理由とされますが、ご自身の症状に基づき、医師と連携して治療継続の必要性を主張することが重要です。
打ち切りを防ぐためには、日頃から症状を正確に伝え記録を残し、保険会社と適切にコミュニケーションを取ることが求められます。
万が一打ち切られても、健康保険への切り替えや弁護士、交通事故紛争処理センターへの相談など、対処法は存在します。
仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください
仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。
お気軽にご相談、ご予約ください。
「整形外科との併用」「正しい通院」を徹底サポート!