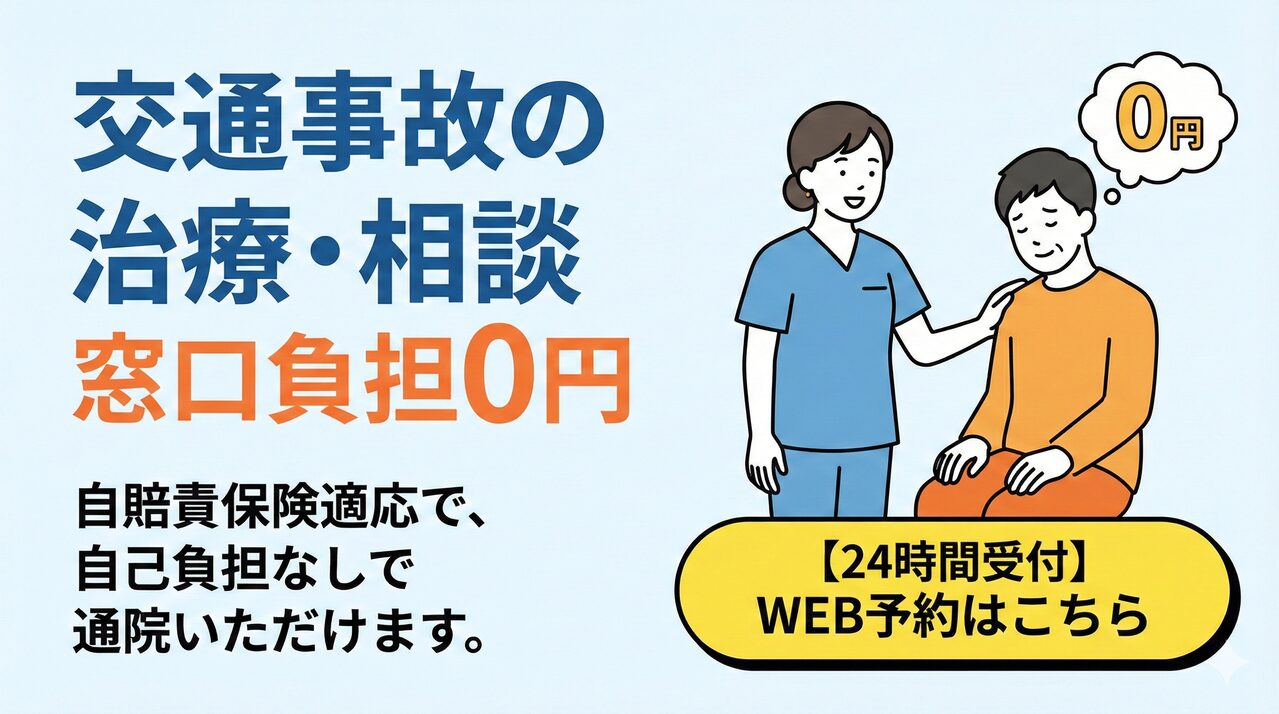交通事故の治療で「健康保険は使えない」と言われたことはありませんか? それは多くの場合誤解です。
この記事を読めば、なぜそう言われるのか、その本当の理由(自由診療、加害者保険、手続き)が分かります。
さらに、健康保険を使うべきケース・使わない方が良いケースの判断基準や、具体的な手続き方法まで詳しく解説。交通事故の治療費で損をしないための正しい知識が身につきます。
交通事故で健康保険は原則使える!「使えない」は誤解
交通事故によるケガの治療に、健康保険は「使えない」と思っていませんか? 実はそれは大きな誤解です。結論から言うと、交通事故によるケガの治療にも、健康保険は原則として使えます。
「交通事故なのだから、加害者が全額負担すべきだ」「健康保険を使うと治療が制限されるのでは?」といった声も聞かれますが、まずは「原則使える」という事実をしっかりと押さえておくことが重要です。
「交通事故に健康保険は使えない」という誤解が広まった背景
では、なぜ「交通事故に健康保険は使えない」という誤解が広まってしまったのでしょうか。主な理由としては、以下のような点が考えられます。
- 一部の医療機関で「交通事故には健康保険は使えません」といった誤った説明がなされることがある。
- 加害者側の保険会社(任意保険会社)が、治療費を直接医療機関に支払う「一括対応」を行うことが多く、被害者が健康保険を使う機会が少ない。
- 健康保険を使うためには「第三者行為による傷病届」という手続きが必要であり、それを知らない、または面倒だと感じる人がいる。
これらの要因が複合的に絡み合い、「交通事故の治療では健康保険が使えない」という誤解が定着してしまったと考えられます。しかし、これはあくまで誤解であり、法的な根拠はありません。
健康保険法における規定と厚生労働省の見解
健康保険が交通事故の治療に使える根拠は、法律や国の通達で明確に示されています。
健康保険法第57条では、保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合(交通事故など)でも、被保険者に対して保険給付を行う義務があると定めています。ただし、その限度において、保険者は加害者(第三者)に対して損害賠償を請求する権利(求償権)を取得します。
また、厚生労働省は、昭和43年の通知において、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりはなく、保険給付の対象となる」という見解を明確に示しており、医療機関に対しても健康保険の利用を拒否しないよう指導しています。
このように、法律上も行政の見解としても、交通事故によるケガの治療に健康保険を利用することは正当な権利なのです。
ただし、健康保険を利用するためには、後述する「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
これは、健康保険組合などが、本来治療費を負担すべき加害者に対して、立て替えた医療費を請求するために必要な手続きです。
なぜ交通事故で健康保険が「使えない」と言われるのか? 本当の理由
交通事故による怪我の治療には、原則として健康保険が利用できます。しかし、医療機関の窓口や保険会社とのやり取りの中で「交通事故には健康保険は使えない」と言われたり、そう思い込んだりしてしまうケースが後を絶ちません。
その背景には、主に以下の3つの理由が考えられます。
【理由1】自由診療を勧められるケースがあるため
交通事故の治療を受ける際、医療機関から健康保険を使わない「自由診療」を勧められることがあります。これが「健康保険は使えない」という誤解を生む大きな要因の一つです。
自由診療とは何か? メリット・デメリット
自由診療とは、健康保険のような公的医療保険が適用されない診療のことです。治療内容や料金設定は医療機関が独自に決めることができます。
健康保険診療との主な違いやメリット・デメリットを理解しておきましょう。
| 項目 | 保険診療 | 自由診療 |
|---|---|---|
| 治療内容の範囲 | 国が定める保険診療のルールに基づく治療 | 保険適用外の治療や先進的な治療など、医療機関が提供できる範囲で選択肢が広い場合がある |
| 治療費の単価(点数) | 診療報酬点数に基づき全国一律(1点10円) | 医療機関が自由に設定可能(一般的に健康保険診療の1.5倍~2倍以上になることも) |
| 窓口での自己負担 | 原則1割~3割負担 | 全額自己負担(ただし、交通事故の場合は加害者側の保険会社が支払うことが多い) |
| メリット | ・治療費を抑えられる ・全国どの病院でも一定水準の治療が受けられる | ・治療の選択肢が広がる可能性がある ・時間をかけた丁寧な診察を受けられる場合がある |
| デメリット | ・受けられる治療や薬に制限がある | ・治療費が高額になりやすい ・治療内容や費用が医療機関によって異なる |
交通事故の場合、自由診療で治療を受けても、最終的に加害者側の保険会社が治療費を負担することが多いため、被害者自身が高額な治療費を直接支払う場面は少ないかもしれません。しかし、後述する過失割合が大きい場合や、治療が長引きそうな場合は注意が必要です。
病院側が自由診療を勧める理由
医療機関側が自由診療を勧める背景には、主に以下のような理由があります。
- 診療報酬が高い
自由診療は健康保険診療よりも高い単価を設定できるため、病院の収益につながりやすい側面があります。 - 治療の自由度が高い
健康保険のルールに縛られず、医師の裁量で幅広い治療を提供できる場合があります。 - 事務手続きの簡略化
保険請求に関する手続きが、健康保険診療に比べて簡略化される場合があります。
ただし、勧められるがまま自由診療を選択するのではなく、本当にその治療が必要なのか、健康保険診療では代替できないのかなどを確認することが大切です。不必要な高額診療につながる可能性もゼロではありません。
【理由2】加害者側の保険会社(自賠責保険・任意保険)が治療費を支払うため
交通事故の損害賠償実務では、加害者が加入している自賠責保険や任意保険会社が、被害者の治療費を医療機関に直接支払う「一括対応」と呼ばれる手続きが広く行われています。
この仕組みが、「健康保険を使う必要がない」あるいは「使えない」という認識につながることがあります。
自賠責保険・任意保険による治療費支払いの仕組み
交通事故の被害者救済のため、まずは強制加入である自賠責保険から治療費などが支払われます(傷害部分の上限は120万円)。多くのケースでは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険分も含めて治療費の支払いを代行します。これが「一括対応」です。
健康保険を使わない場合の治療費の流れ
保険会社による一括対応が行われる場合、被害者は医療機関の窓口で治療費を支払う必要がなくなります。
保険会社が医療機関から診断書や診療報酬明細書(レセプト)を取り寄せ、内容を確認した上で直接支払いを行います。このため、被害者にとっては手間がかからず、一時的な立て替え負担もないというメリットがあります。
結果として、あえて健康保険を使うという発想に至らない、あるいは保険会社から「こちらで対応しますので健康保険は使わないでください」といった案内を受ける場合があるのです。
【理由3】手続き(第三者行為による傷病届)が必要なため
交通事故のように、第三者(加害者)の行為によって負傷し、その治療に健康保険を使用する場合には、被害者が加入している健康保険組合や市区町村(国民健康保険の場合)に対して、「第三者行為による傷病届」を提出する義務があります。
この手続きの存在や、その手間が、健康保険利用のハードルとなっている側面があります。
第三者行為による傷病届とは
「第三者行為による傷病届」は、健康保険を使って治療を受けた際、その原因が第三者の行為によるものであることを、保険者(健康保険組合など)に届け出るための書類です。
この届出に基づき、保険者は一時的に立て替えた医療費(保険給付分、つまり治療費全体の7割~9割)を、後日、加害者(またはその保険会社)に請求(求償)します。
これは、本来加害者が負担すべき費用を健康保険が一時的に負担した形になるため、その費用を回収し、保険財政の健全性を保つために必要な手続きです。
届出をしない場合の問題点
この届出を怠ると、保険者は加害者側へ医療費の求償を行うことができません。そのため、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 健康保険の使用が認められず、医療機関から自由診療扱いとされる。
- 後日、保険者から立て替えた医療費の返還を求められる。
- 医療機関によっては、届出の提出を健康保険適用の条件としている場合がある。
手続きが面倒に感じられるかもしれませんが、健康保険を利用する際には必ず必要な手続きです。不明な点は、加入している健康保険組合や、市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせましょう。
交通事故で健康保険を使うべきケースとは?
交通事故の治療において、健康保険は原則として利用できます。しかし、状況によっては健康保険を使わずに治療を進めることもあります。
ここでは、被害者の方が積極的に健康保険の利用を検討すべき具体的なケースについて解説します。
加害者が不明(ひき逃げなど)の場合
残念ながら、ひき逃げや当て逃げのように、加害者が特定できない交通事故も発生します。この場合、治療費を請求する相手がいないため、加害者側の自賠責保険や任意保険からの支払いを受けることができません。
このような状況では、ご自身の健康保険を利用して治療を受けるのが現実的な選択肢となります。健康保険を使えば、医療機関の窓口での負担は原則1割から3割で済み、高額になりがちな治療費の自己負担を大幅に抑えることができます。
なお、加害者が不明な場合や無保険の場合には、政府の「自動車損害賠償保障事業」に対して損害賠償額を請求できる制度もありますが、手続きに時間がかかる場合や、支払われるまでに立て替えが必要になるケースも考えられます。
まずは健康保険を利用して治療を開始し、自己負担を抑えることを優先しましょう。
加害者が無保険の場合
交通事故の加害者が、強制保険である自賠責保険に加入していない、あるいは任意保険に加入していないケースも考えられます。地域差はありますが、全国的には約25%の運転手は任意保険未加入だと言われています。
加害者が自賠責保険に加入していない場合(無保険車事故)は、前述の「自動車損害賠償保障事業」への請求が可能ですが、任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の支払い限度額(傷害部分で120万円)を超える損害について、加害者本人に直接請求することになります。
しかし、加害者に十分な支払い能力がない場合、治療費や慰謝料などを回収できないリスクがあります。このような場合も、健康保険を利用して治療を受けることで、当面の治療費負担を軽減することが重要になります。
被害者の過失割合が大きい場合
交通事故では、被害者側にも一定の過失(不注意)が認められるケースがあります。例えば、信号無視や飛び出しなどが該当します。
このような場合、ご自身の過失割合に応じて、受け取れる損害賠償金(治療費を含む)が減額されます。これを「過失相殺」といいます。自賠責保険でも過失が30%以上の場合は20%減額され、傷害部分の補償上限は120万円から96万円になります。
もし健康保険を使わずに自由診療で治療を受けていると、治療費が高額になりがちです。その高額な治療費に対して過失相殺が適用されると、被害者の自己負担額が予想以上に大きくなってしまう可能性があります。
一方、健康保険を利用すれば、自由診療に比べて診療報酬点数が低く抑えられます。そのため、過失相殺によって治療費が減額されたとしても、最終的な自己負担額を低く抑えることができる可能性が高まります。
ご自身の過失割合が大きい、または大きくなる可能性があると感じる場合は、健康保険の利用を積極的に検討しましょう。
治療が長引き、自賠責保険の傷害部分の上限額(120万円)を超えそうな場合
交通事故の損害賠償において、まず適用されるのが加害車両にかけられている自賠責保険です。しかし、自賠責保険には支払い限度額が定められており、傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料など)については、被害者1名あたり120万円が上限となっています。
むちうちなどの比較的軽傷なケースでも、治療が長引けば治療費がかさみます。また、骨折などの重傷を負った場合は、入院や手術が必要となり、治療費が高額になる傾向があります。
健康保険を使わずに自由診療で治療を続けていると、診療単価が高いため、早期に自賠責保険の上限額120万円に達してしまう可能性があります。上限を超えた分については、加害者の任意保険や加害者本人に請求することになりますが、交渉が難航するケースも考えられます。
健康保険を利用すれば、診療単価が抑えられるため、治療費の総額を低く抑えることができ、自賠責保険の120万円の範囲内で治療を続けられる可能性が高まります。また、万が一上限額を超えてしまった場合でも、健康保険を利用していれば自己負担額を軽減できます。
交通事故で健康保険を使わない方が良いケース(注意点)
交通事故の治療において、健康保険は原則として利用できますが、状況によっては健康保険を使わない方が良い、あるいは利用に際して注意が必要なケースも存在します。
安易に判断せず、ご自身の状況に合わせて慎重に検討しましょう。
自由診療の方が適切な治療を受けられる可能性がある場合
健康保険を使った保険診療では、治療内容や使用できる薬剤に一定の制限があります。一方で、自由診療では、保険適用外の最新治療や先進的な治療法を選択できる可能性があります。
例えば、まだ一般的に普及していない特殊なリハビリテーションや、海外で承認されているものの国内では未承認の薬剤などを用いた治療を希望する場合、自由診療を選択することになります。
ただし、自由診療は治療費が全額自己負担となり、高額になる傾向があります。また、「自由診療=最善の治療」ではありません。現在の医療では「標準治療=最善の治療」となっています。
症状によっては保険診療で十分な効果が得られることも多く、不必要な検査や過剰な治療が行われるリスクも考慮する必要があります。
自由診療と保険診療の違いや併用(混合診療)については、厚生労働省のウェブサイトでも情報提供されています。治療方針については、医師と十分に相談し、メリット・デメリットを理解した上で判断することが重要です。
加害者側の保険会社が治療費全額をスムーズに支払う場合
加害者が任意保険に加入しており、その保険会社が「一括対応」として医療機関に直接治療費を支払ってくれる場合があります。この場合、被害者は病院窓口での支払いが不要となり、「第三者行為による傷病届」などの健康保険利用のための手続きを行う手間も省けます。
一見すると便利な仕組みですが、注意点もあります。
一括対応はあくまで保険会社のサービスであり、法的な義務ではありません。保険会社側の本当の目的は、一括対応を利用して損害賠償額のコントロールを行い、総額を自賠責保険の補償上限内に収めることです。
保険会社は営利企業であることを忘れてはいけません。
そのため、以下のようなケースでは、途中から対応を打ち切られたり、最終的に支払われた治療費の一部を被害者が負担(求償)されたりする可能性があります。
- 被害者の過失割合が大きい場合
- 治療が不必要に長引いていると保険会社が判断した場合
- 治療費が高額になり、自賠責保険の傷害部分の上限額(120万円)を超え、かつ任意保険の支払い基準でも争いが生じる可能性がある場合
特に、過失割合に争いがある場合や、治療が長引くことが予想される重傷事故の場合は、安易に任意一括対応に頼るのではなく、当初から健康保険を利用することを検討する方が、最終的な自己負担額を抑えられることがあります。
健康保険を利用すれば、少なくとも治療費の自己負担割合(通常3割)を超える部分については、保険会社との交渉がまとまるまで支払いを保留できます。
任意一括対応を受けている場合でも、後から健康保険利用に切り替えることは可能です。
治療費の支払われ方に不安がある場合は、早めに加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険の窓口、または弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
交通事故で健康保険を使う際の手続きと流れ
交通事故の治療で健康保険を利用する場合、通常とは異なる手続きが必要になります。これは、本来加害者が負担すべき治療費を、健康保険が一時的に立て替える形になるためです。
スムーズに手続きを進めるための手順を解説します。
まずは加入している健康保険組合(協会けんぽ、国民健康保険など)に連絡
交通事故で健康保険を使用したい場合は、まずご自身が加入している健康保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、市区町村の国民健康保険担当課、共済組合など)に連絡を入れましょう。保険証に記載されている保険者の名称を確認し、連絡先を調べてください。
連絡の際には、以下の点を伝えるとスムーズです。
- 交通事故に遭い、治療のために健康保険を使用したいこと
- 事故の発生日時、場所、状況の概要
- 加害者の情報(氏名、連絡先、加入している保険会社など、わかる範囲で)
- 受診する(または受診した)医療機関名
保険者から、今後の手続きについて具体的な指示がありますので、それに従ってください。特に「第三者行為による傷病届」の提出を求められます。
「第三者行為による傷病届」の提出
健康保険を使って交通事故の治療を受けるためには、「第三者行為による傷病届」を加入している保険者に提出する必要があります。
「第三者行為」とは、交通事故のように、他人の行為によって傷病を負った場合を指します。この届出により、保険者は一時的に立て替えた医療費を、後日加害者(または加害者の加入する自賠責保険・任意保険)に対して請求(求償)することができるようになります。
必要書類と記入内容
「第三者行為による傷病届」の提出には、通常、以下の書類が必要となります。
書式や必要書類の詳細は加入している保険者によって異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。書類は保険者のウェブサイトからダウンロードできる場合が多いです。
| 書類名 | 主な記入内容・入手先 |
|---|---|
| 第三者行為による傷病届 | 被害者(被保険者)の情報、加害者の情報、事故発生状況、負傷の状態などを記入します。保険者から入手します。 |
| 事故発生状況報告書 | 事故の詳しい状況(図を含む場合あり)、過失割合に関する情報などを記入します。保険者から入手します。 |
| 同意書(念書) | 保険者が加害者側へ医療費を請求すること、およびそのために必要な情報の取得について同意する書類です。保険者から入手します。 |
| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センターが発行する、交通事故があった事実を証明する書類です。警察への届出後、申請により取得できます。原則として原本の提出を求められます。 |
| その他 | 保険証のコピー、示談書のコピー(示談成立済みの場合)などが求められることがあります。 |
記入にあたっては、事故の状況や相手方の情報を正確に記載することが重要です。不明な点があれば、保険者の担当窓口に問い合わせましょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトでも、手続きに関する情報が公開されています。
提出先と提出期限
「第三者行為による傷病届」と関連書類は、ご自身が加入している健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ支部、市区町村の国民健康保険担当課など)に提出します。
提出期限については、「遅滞なく」提出することが求められています。明確な期限が定められていない場合が多いですが、事故後できるだけ速やかに提出することが望ましいです。
提出が遅れると、保険者から加害者側への請求手続きが遅れたり、最悪の場合、健康保険が使えなくなる可能性も否定できませんので注意が必要です。
医療機関の窓口での手続き
交通事故の治療で医療機関を受診する際には、窓口で健康保険を使用したい旨を明確に伝えてください。その際、必ず健康保険証を提示します。
医療機関によっては、「交通事故の場合は健康保険を使えない」と誤解しているケースも稀にあります。
もし使用を拒否された場合は、「加入している健康保険組合(または協会けんぽ、市区町村)に連絡し、健康保険を使用できること、および『第三者行為による傷病届』を提出する(または提出済みである)ことを確認済みです」と説明しましょう。それでも理解が得られない場合は、加入している保険者に相談してください。
健康保険を使用することで、窓口での自己負担は原則として医療費総額の3割(年齢や所得により異なる)となります。
労災保険が適用される場合の健康保険との関係
交通事故が仕事中や通勤中に発生した場合、健康保険ではなく「労災保険(労働者災害補償保険)」が適用されます。
ここでは、労災保険と健康保険、そして自賠責保険との関係について解説します。
通勤中や業務中の交通事故は労災保険が優先
労働者が業務上の理由や通勤によって負傷した場合(業務災害・通勤災害)、その治療には原則として健康保険ではなく労災保険が適用されます。これは法律で定められており、労働者を保護するための制度です。
例えば、会社の車で営業先に向かう途中の事故(業務災害)や、自宅から会社へ公共交通機関で向かう途中の事故(通勤災害)などが該当します。このようなケースでは、健康保険を使用することはできません。
労災保険の対象となる「通勤」の定義など、詳細については以下を確認しましょう。
もし誤って健康保険を使って治療を受けてしまった場合は、速やかに加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口、そして勤務先に連絡し、労災保険への切り替え手続きを行う必要があります。
労災保険と健康保険は併用できない
同一の傷病(ケガや病気)に対して、労災保険と健康保険の両方から給付を受けることはできません。これは「二重給付の禁止」と呼ばれる原則です。
業務災害や通勤災害と認定される交通事故の治療については、労災保険が優先的に適用されるため、健康保険を使うことは原則として認められません。
治療費の自己負担分についても、労災保険から給付されるため、健康保険の給付(高額療養費制度など)を受けることもできません。
労災保険と自賠責保険は併用できる
労災保険と自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、それぞれ制度の目的や補償内容が異なるため、併用(調整)して利用することが可能です。
一般的には、まず労災保険から治療費や休業補償などの給付を受けます。その後、労災保険から支払われた金額について、労災保険(国)が加害者側の自賠責保険に対して求償(支払った分の請求)を行います。
また、労災保険では補償されない損害(例:慰謝料)や、労災保険の給付額だけではカバーしきれない損害については、被害者自身が加害者側の自賠責保険や任意保険に請求することができます。
| 保険の種類 | 健康保険との関係 | 自賠責保険との関係 | 主な補償内容 |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 併用不可(労災優先) | 併用(調整)可能 | 治療費、休業補償、障害補償、遺族補償など(慰謝料は対象外) |
| 健康保険 | – | 併用可能(第三者行為による傷病届が必要) | 治療費(一部自己負担あり) |
| 自賠責保険 | 併用可能(第三者行為による傷病届が必要) | – | 治療費、休業損害、慰謝料など(傷害部分の上限120万円) |
どちらの保険をどのように利用するかは、事故の状況や損害の内容によって異なります。複雑なため、勤務先の担当者や労働基準監督署、または交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
自賠責保険の詳細については、国土交通省のポータルサイトも参考にしてください。
交通事故の健康保険利用でよくある質問
交通事故で健康保険を利用する際に、多くの方が疑問に思う点について解説します。
健康保険を使うと治療内容に制限はありますか?
原則として、健康保険を使って受けられる治療内容に、交通事故だからという理由での特別な制限はありません。医師が必要と判断した、健康保険の適用範囲内の検査や治療(投薬、手術、リハビリテーションなど)は通常通り受けることができます。
ただし、健康保険が適用されない先進医療や、個室利用時の差額ベッド代、接骨院・整骨院での一部の施術などは対象外となります。これは交通事故以外の病気やケガで健康保険を利用する場合と同様です。
自由診療でなければ受けられない特殊な治療を希望する場合は、健康保険の適用外となります。
詳しくは、治療を受ける医療機関や、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
健康保険を使った場合、示談交渉に影響はありますか?
健康保険を利用したことが、示談交渉において被害者にとって不利になることは基本的にありません。むしろ、メリットとなる場合があります。
健康保険を利用すると、自由診療に比べて治療費の単価が抑えられます。もし被害者側にも過失割合がある場合、治療費総額が低くなることで、最終的に自己負担しなければならない金額が減る可能性があります。
健康保険組合等は、支払った医療費(保険給付分)について、後日加害者(または加害者の保険会社)に対して請求(求償)します。この請求手続きのために「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。健康保険を使ったからといって、加害者が支払うべき損害賠償額が減るわけではありません。
ただし、示談交渉においては、治療費だけでなく、慰謝料や休業損害など様々な要素が絡んできます。不明な点や不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
病院が健康保険の使用を拒否した場合どうすればいいですか?
保険医療機関(健康保険を扱える病院や診療所)は、正当な理由なく健康保険の利用を拒否することは、原則として認められていません(保険医療機関及び保険医療養担当規則)。
もし病院の窓口で「交通事故では健康保険は使えない」と言われた場合は、まず以下の対応を試みてください。
- 理由を確認する
なぜ健康保険が使えないと言われたのか、具体的な理由を確認しましょう。「交通事故だから」という理由だけであれば、それは誤解である可能性が高いです。 - 説明する
厚生労働省の通達などに基づき、交通事故でも健康保険が使える原則であることを丁寧に説明します。加入している健康保険組合等に事前に連絡し、その旨を伝えておくのも有効です。 - 相談する
それでも病院側が健康保険の使用を認めない場合は、加入している健康保険組合(協会けんぽ、国民健康保険の窓口など)や、管轄の地方厚生(支)局に相談してください。適切な対応についてアドバイスをもらえます。
「第三者行為による傷病届」の提出がまだの場合、それを理由に難色を示されることもありますが、手続き中であることや、後日速やかに提出することを伝えましょう。
まとめ
交通事故の治療に健康保険は原則として利用できます。
「使えない」と言われる主な理由は、医療機関から自由診療を勧められるケースがあること、加害者側の自賠責保険や任意保険が治療費を支払う前提があること、そして「第三者行為による傷病届」の提出が必要なためです。
しかし、ご自身の過失割合が大きい場合や治療が長引く場合などは、健康保険を利用した方が有利になる可能性があります。
まずは加入する健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険の窓口に連絡し、必要な手続きを確認しましょう。
仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください
仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。
お気軽にご相談、ご予約ください。
「整形外科との併用」「正しい通院」を徹底サポート!